子どもの「精神障害」はかなり誤解されている 児童精神科医・滝川一廣さんが語る「歴史」
――「貧困・格差の一定以上の解消をはかる政治的、経済的な施策なくしては、いかなる『先進的』な(虐待)防止対策も焼け石に水かもしれない」と書いていますね。滝川さんは虐待防止法以前、1980年代には児童相談所に勤務する児童精神科医でした。
摘発型の虐待防止では、子育ての失調は防げない。当時、イライラして、赤ちゃんの指をかみ切ってしまったお母さんがいた。今だったら、すぐに虐待だと判断されて、子どもは取り上げられてしまう。でも、この時は親子関係の失調として、その間を取り持つ支援をしました。子どもを分離せずに育てることができました。
今は虐待という言葉が一般的になり、一方的に親が悪いというイメージが広がりました。親である以上、子どもをしっかり育てなければという圧力はとても強い。愛情と責任さえあれば、子どもは育つという一種の思い込みがあります。うまく育たないと、愛情か責任感に欠けた親だと言って責める。
虐待という言葉はよくないです。虐待と名付けるとその家族を否定的に見る。あなたは悪いことをしているというまなざしの中で家族統合といってもうまくいかない。
でも、子どもはそれぞれ違っていて、同じように育てれば同じように育つというわけではないのです。また、こういう人生が幸福だという模範解答はない。それぞれに与えられた条件があり、それぞれの子どもが持っている力があり、親の置かれている条件がある。
そのなかで、今、この子はこれ以上頑張るのは難しいとか、この子なら背中を押してあげれば立てそうだとかということがあります。何がいいかはそのときどきで変わる。その判断を全部親がしなければいけないというのも大変なことですね。
だからこそ、親一人の子育てには無理があるということです。『子どものための精神医学』は、分類して、この子育てが正しいと白黒つけて安心するための本ではなく、白と黒の間を埋めていくための本です。
サポートがあれば、なんとかしのいでいける
――どのような社会的な支援があるといいのでしょうか。
妊娠した時から全員に専門家がかかわり始めるサポートがあるといいと思う。抱っこが下手でもサポートがあれば、なんとかしのいでいける。大丈夫な親子から手放していけばいい。こじれてから支援をするよりも、費用対効果としてもずっといいのではないかと思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

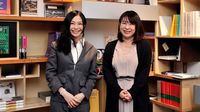





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら