その一方で、JR東日本のある労働組合幹部は、過半数代表者についてこんな認識を持っている。
「過半数代表者の権限が『労使協定の締結』などに限定されていることは、私たち組合も承知しています。しかしながら、その権限が限られているとしても、過半数代表者は、その職場に過半数組合がない場合において、アルバイトやパートも含めすべての労働者を代表する存在です。会社側との協定の締結において、過半数代表者は過半数組合と同様の役割を求められていると私たちは認識しています」
この労組幹部の言う「過半数組合と同様の役割」とは具体的に何を指すのか。幹部が続ける。
「例えば、私たち組合が会社と36協定を締結する際には、長時間労働による過労死や過労自殺を未然に防ぐために、その職場の時間外労働の実態をチェックした上で、締結に臨みます。
また同じ職場でも、仕事量の偏りや経験年数のバラつきなどを背景に、36協定における時間外労働の上限について、『もっと引き下げるべき』という人もいれば、『現状を維持すべき』という人もいる。組合は、そういった個々の職場の様々な意見を集約した上で、協定の締結に臨む。過半数代表者にも当然、そうした職場の意見集約が求められるはずなのですが、社友会会員が過半数代表者に就いた職場では、それができていないところがほとんどなのです」



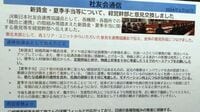




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら