数学ができる人の共通点「数字のセンス」の正体 東大生は文系でも"匂いでかぎ分け"間違い防ぐ力が身に付いている
要するに、「2」「3」「5」「6」「7」の5択でも、数が小さい順に答えになりやすいと考えることができるわけですね。
万能ではないが、違和感にはなる
もちろんこの話はまったく万能な話ではありません。でも、計算をしていると感覚的に、「ああ、この数字が答えになりそうだな」というのはわかってきてしまいます。逆に、計算した結果として「√7」になったとして、「√7ってことは、7が計算の中に出てきたわけだよな。どこ由来の7だったんだっけ、これ?」というように、頭の中で「チェック」が行われることになります。
このチェックのことを「検算」または「試し算」と呼ぶわけですが、時間との戦いであるテストの中で、すべての数字にチェックをしていくわけにはいきません。特徴的な数字や、自分の経験則から外れた数字が答えになったときに、「√7?なんかこれミスってないか?」という「勘」を働かせることができるわけです。
数字のセンスがあるというのは、このような「勘」が働きやすい人のことを言います。「この数字がここで出るのは変だな」と感じ、違和感を拾うことができる人は、計算が間違っているときに「待てよ?この問題の設定で7は出るはずないぞ」と感じ、検算に移れるわけですね。
今回は√を例に出して話しましたが、別にそれ以外の場合も考えられます。計算ミスが少なくなり、点数が高くなりやすいわけです。ぜひ参考にしてみてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



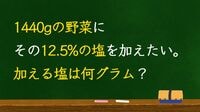



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら