数学ができる人の共通点「数字のセンス」の正体 東大生は文系でも"匂いでかぎ分け"間違い防ぐ力が身に付いている
それはなぜかというと、√の計算は足し算とか引き算で答えを出すことが少なく、掛け算割り算が基本となるので、基本的には計算をしていて今まで登場した数字の約数が答えになりやすいからです。
「√2+√3=√5」にはならないため、基本的には掛け算で計算した結果の数字に5が含まれていないと答えにはならないのです。(後ほど例外については触れます)
例えばいろんな辺の長さや面積を掛け算した結果として、「√45」になって、答えが「√45=3√5」となる……というようなことでしか「√5」は答えにならないのです。
5や7は1桁台の素数の中では大きい数になるので、そもそも問題文を見て、「Aの辺は15cm」とか「21分後にボタンを押す」のように5や7を約数に持つ計算が絡まない問題であると判断した場合は、あまり答えになり得ないんじゃないかな?という予想をつけることができます。
もちろんこの話は例外もある話で、例えば余弦定理を使って辺を出す場合には+も-もたくさん登場するのですが、しかし逆に言えばそういう計算をしていないのに√5や√7が答えになっているとなったら、「ちょっと警戒するべきかも。どこかで間違えていないかな」と考えることができます。
一番答えになりやすい数字は…?
それに対して、例えば一番答えになりやすいのは「2」です。2は、√8=2√2や√18=3√2のように、計算している中でかなり多く登場することのある数字です。偶数が出てくるときには2が答えになる可能性はあるな、と思いながら問題を解くことになります。
3も、2よりも答えになる確率自体は少なそうな感覚がありますが、√12=2√3や√27=3√3のような計算で登場する可能性があるので、他の数字と比べて出現頻度が高いです。奇数の計算をしているときにはなんとなく答えになるかも?と思いながら解くことになります。
この観点で行くと、「6」は答えになりやすい「2」と「3」の掛け算なので、3番目に答えになりやすい数字だと考えることができます。



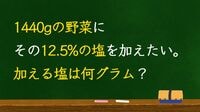



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら