数学ができる人の共通点「数字のセンス」の正体 東大生は文系でも"匂いでかぎ分け"間違い防ぐ力が身に付いている
共通テストやセンター試験の数学では、選択問題が多く出題されます。
その中でも“数字のセンス”が如実に表れるのが、「√(ルート)」が登場する問題です
前提として、共通テストの数学では、1桁の数字と2桁の数字が明確に決まっており、「√ア」で「アに当てはまる数字は?」と聞かれているときには「0-9」までの数字を選び、「√イウ」で「イウに当てはまる数字は?」と聞かれているときには「11-99」までの数字を選ぶ必要がある、という問題になっています。
√(ルート)が出てくると、選択肢は一気に狭まる?
「√ア」で「アに当てはまる数字は?」と聞かれているときには基本的に「0-9」までの数字なので10択と思われるかもしれませんが、実際はそんなことはありません。まず、「0」はないですね。√0=0だからです。
1も、√1=1なのであり得ない。
4は、√4=2なのでこれもあり得ません。
8は√8=2√2、9は√9=3なのであり得ない。
となると、「2」「3」「5」「6」「7」が正解になるので、実質的には5択になります。
2桁の数でも同様で、「12, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 32, 36, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 64, 68, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 99」の35個は「√a = k√b」のように数が変わってしまうので答えにはなりません。意外と削れる数があるわけですね。
ここまでは簡単な話なのですが、東大生の間で話題になるのは、1桁の√を答えるとき、「5」「7」は、あんまり共通テストで正解にならないよね、という話です。
答えになり得ない、とまでは言えないのですが、2や3に比べて、5や7というのは計算の際に「これは5とか7じゃなさそうだな」という匂いがなんとなくわかってしまうという話です。



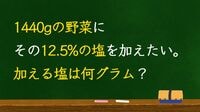



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら