大学入試で優位な面も、授業料無償化で人気低迷の「都立高」知られざる魅力 私立単願に落とし穴、「指定校推薦枠」にも注目
入試形態別の追跡データを分析しているという私立高校の先生も、こっそりこう打ち明ける。
「都立高校受験組と私立単願組では、大学進学時に明確な差が出ています。一般入試でも指定校推薦でも、高校受験期に最後まで勉強していた生徒が有利です」
生徒も保護者も、こうした事実を知らない。
私立高校が単願制度を維持するのは、「学力」ではなく「生徒数の確保」が経営上の最優先事項だからだ。とくに中堅以下の私立高校は、無償化政策の恩恵を受けることで経営優先の姿勢を強めており、学力保障という本質的な視点が抜け落ちている。
日本維新の会が掲げる「教育無償化」政策は教育の機会均等を目指すが、先行する東京都では、実際には「勉強回避のスキーム」として機能してしまっている。東京都の教育現場で起きているこの変化は、全国で起こり得る課題の縮図でもある。政治に関わるすべての人たちに、この現実を直視してほしい。
最先端の授業や豊富な指定校推薦枠、注目の都立高とは?
メディアも都立高校を取り上げる際は、日比谷高校の東大合格者数や国際高校の海外名門大学への進学実績といった進学校の企画に集中しがちだ。こうした報道は「有名都立高校に入学できるならよいが、そうでないなら不安だ」という空気を生み、中学受験熱をあおるとともに、安易な私立単願への流れを助長していると感じる。
だからこそ、あえて主張したい。「勉強が得意ではない普通の子こそ、都立高校ルートを選ぶべきではないか」と。学力中堅層以下の私立単願が増えた今、都立高校を選択することの意味と優位性を見直すべきだ。
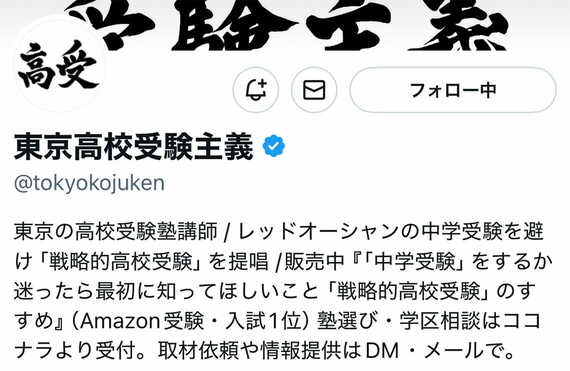
(写真:Xより)
昨年、府中市の都立農業高校を訪問した。同校初の塾対象説明会だったというが、参加者は私を含めてわずか3人。進学校として認知されていない同校は、受験業界ではほとんど黙殺されているに等しいのが現状だ。
しかし、同校の現実は私の固定観念を覆すものだった。世界最先端の「スマート農業」を教育に取り入れ、広大な農園には気象センサーを設置、データはクラウドで管理している。生徒たちは1人1台のタブレット端末を駆使し、データ分析や仮説検証に取り組む。
早稲田大学理工学術院先進理工学部との連携による大豆栽培研究、東京農工大学との稲の栽培実習、さらにはオーストラリアでの循環型経済視察や英語プレゼンテーションなど、国際的な学びの場も提供されている。
注目すべきは進路実績だ。こうした都立専門高校は、かつては「職業高校」として扱われていたが、今や大学指定校推薦枠が大幅に拡充されている。
例えば、都立園芸高校(世田谷区)からは例年、大学進学者の3割から4割が東京農業大学へ総合型選抜や指定校推薦で進学しており、実質的に「半附属校」ともいえる存在だ。同大の一般入試合格者数ランキングに目をやると、桜美林、小松川、桐蔭学園、成城、朋優学院といった普通科進学校が並ぶが、農業高校の生徒たちがこれらの普通科進学校と肩を並べることができるのは、専門教育で培ったモチベーションと実践力が評価されているからである。































