注目の「公立高校の併願制」、"新たな恩恵"と"偏差値至上主義の助長"への懸念 個性の時代に合った公平な制度をつくるには?
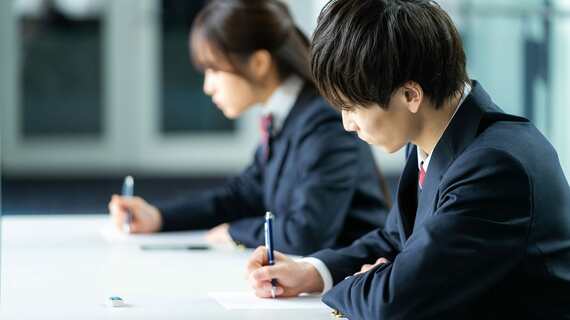
今話題の「併願制」、過去に都立高入試でも採用されていた
実は、都立高校は1994年に「単独選抜」(単願制)が始まるまで、「併願制」を採用していた時代があった。
とくに、都立高校における「黄金期」と呼ばれる1950~1960年代半ばは「学区合同選抜」という名の併願制を採用しており、受験生は第1志望校に不合格だったとしても、学区内合格者であれば第2志望校に進学することができた。
ところが、「名門校への優秀層の集中を防ぐ」という名目の下、1967年より悪名高き「学校群制度」に移行する。これは、各学区の高校を2~3校を束ねて「群」を作り、受験生に群を選択させる制度だ。
学区合同選抜と大きく異なるのは、受験生が志願先を選べない点にある。例えば11群(日比谷・九段・三田)を受験した場合、成績順に群内の高校に振り分けられるので、どこに入学できるかは結果が出るまでわからない。いわば“くじ引き入試”と化し、「野球部に入りたかったのに、野球部のない学校に回された」などの嘆きが相次ぎ、都立のブランド力は見る間に失速した。
東京都はさまざまな課題を抱える学校群制度を放置し続けたが、1982年にようやく廃止。学区合同選抜と近い「グループ合同選抜」に移行し、併願制を復活させたのである。
↓
1967年~:学校群制度
↓
1982年~:グループ合同選抜(併願制)
↓
1994年~:単独選抜(単願制)
だが、仕組みをいじる一方で、教育の“中身”を刷新しようとしなかった結果、都立離れは止まらなかった。学区トップ校でさえ定員割れが恒常化し、例えば「2番手校に落ちたのに、空きの出たトップ校に合格」といった矛盾が多発。制度への不信はやがて「併願制=都立低迷」という負のイメージを定着させた。
併願制で「確実な収容」→単願制で「個性に応じた選択」へ
では、なぜ単独選抜へ移行した1994年以前の都立高校で、併願制や、生徒の進学先を振り分ける学校群制度が長く採用され続けたのか。私は、高校入試が「確実な収容」、すなわち「できるだけ多くの受験生を都立高校に振り分ける」という行政的な要請を優先してきたからだと考えている。
戦後の大都市圏では中学校卒業者の急増に高校の整備が追いつかず、「高校不足」は深刻な社会課題であった。その象徴が、公立高校の大増設である。第1次ベビーブーム世代が高校進学期を迎えた1962年、東京都内の中学校卒業生はおよそ18万人。現在のおよそ2倍である。彼らの高校進学に対応するため、東京都は1956年から1970年のわずか14年間で、実に39校もの都立高校を新設した。
併願制は、こうした時代背景の下、「できるだけ多くの受験生を高校へ振り分ける」機能として活用されたのである。専門高校における教育の個性は当時もあったとはいえ、「個性に応じた高校選び」よりも、「確実な収容」が重視された時代だったと言える。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら