Aマッソ加納「後悔は芸人の宿命なのかもしれない」 芸人がこの世で一番最高な仕事だと信じてる
お調子者の私にとっては、そういった温室ともいうべき環境でぬくぬくと3年間を過ごしたことが、「この先もずっとこんな感じでアホみたいに過ごせたらええなあ」という感情を積み上げさせた。クラスには自分より面白い奴もいたし、自分より華があって人前に立つのにふさわしい奴もいた。
しかし誰も芸人にならなかった。私だけが芸人になった。きっと少しだけ、自分自身に対する期待値がまわりの友達より大きかったのだ。そして何より、日常の中で交わされる意味をもたないやり取りに固執していた。誰の心にも一瞬しか咲かなかった言葉たちが私の中でだけ沈殿していき、取り出して遊びたいと思ったときには誰もいなくなっていた。
高校卒業間近、友達との会話
高校3年の卒業間近、友達数人で「これからうちら、どうなっていくんやろうなぁ」と不毛な感傷に浸っていたら、そこにいた沙希子が「卒業したら、両親が離婚する予定やねん」と打ち明けた。
沙希子の両親は彼女が中学生の頃からずっと会話がない冷めきった夫婦だったが、彼女の高校卒業までは別れずにお互い「子育ては最後までやりきった」としたいらしかった。
沙希子はつとめて明るく話していたが、ボソッと漏らした「もう卒業せんとダブったろかな」が本音であると思った。それを聞いて、どう反応すればいいかわからず困惑している私たちの空気を察して、沙希子は「でもそうなったら1人だけジャージの色ちがうの耐えられへんか」と言った。するとその場にいた好美が「おい!」と大きい声を出した。好美は留年していて1つ年上であったので、みんなが赤いジャージを穿いている中で、平然と緑のジャージを穿いていた。
その「おい!」の声で、私もほかの友達も笑った。笑いながら、私は笑いの力を目の当たりにして、美しさと悔しさで泣きそうになった。その場を助けた「ジャージの色ちがうの耐えられへん」も「おい!」も、できることなら私が言いたかった。ぼーっとしてないで、自分の言葉で優しい沙希子を救いたかった。
今日もどこかに、沙希子のような子がいるかもしれない。私は多くの後悔にまみれながらも、いつかの後悔に突き動かされるようにして、最高の仕事を続けていく。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

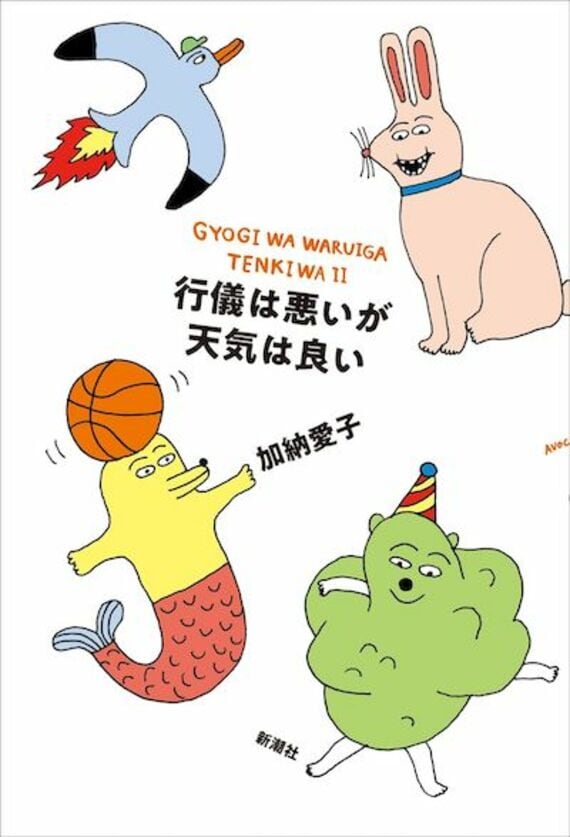































無料会員登録はこちら
ログインはこちら