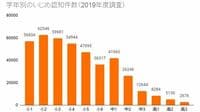不登校経験者の運転士たちが立ち上げた学び場 「僕たち自身、好きな鉄道に救われて元気になれた」
子どもたちの自由度を守りたいので、カリキュラムは決めていません。子どもたちがやってみたいことなら何でも応援できるように、準備を進めているところです。とはいえ、きっと想像もしていないようなリクエストがくるのでしょうね。そう思うと、わくわくします。僕は「支援」という言葉が苦手なんです。学校へ行っていようがいまいが、子どもは大人に手を貸してもらいながら大きくなるのがあたりまえ。特別なことではありません。
もっといえば、大人も子どもといっしょに育っていくもの。AOiスクールも、そんなスタンスでやっていきたいと思っています。
同じ趣味を楽しめる仲間
カリキュラムはないのですが、鉄道会社が手がけるスクールなので、フックとなるのはやはり「鉄道」です。鉄道好きの子どもたちと「同じ趣味を楽しめる仲間」として活動しながら、「鉄道には地理や歴史だったり、機械の仕組みだったり、マナーだったり、いろいろな学びが隠れているよ」ということを自然に伝えられたらうれしいですね。
会社には、鉄道関係の古い本など「お宝」がたくさんあるので、そういうものもスクールに持ち込む予定です。もちろん、鉄道に興味がなくても大歓迎です。小田急グループはさまざまな事業を手がけているので、鉄道事業以外のどこかにつなぐこともできるかもしれません。
――別所さんご自身も中学3年間不登校だったとうかがいました。当時何があったのですか?
僕は、中学受験をして「自由な校風」を謳っている中高一貫校に入学したのですが、いざ入ってみたら、その雰囲気が自分にはまったく合いませんでした。中学3年間、ほとんど学校へは行っていません。
休み始めた当初は苦しかったですね。「不登校」という言葉にはネガティブなイメージがつきまとっているような気がして、その言葉に属している自分がイヤだったんです。その一方で、学校に通い続ける意味も見い出せなくて。不登校だと言われるのもイヤ、学校へ行くのもイヤ、という状況を苦しく感じていました。今でも「不登校」という言葉は、あまり好きではありません。まるで学校へ行くことが大前提であるかのように、「登校」という言葉が「不」という文字で打ち消されていますよね。もっとちがう言葉はないものかと思います。
両親も最初は悩んだと思うし、「行け」と言われたこともあったのですが、だんだんといつも通りに接してくれるようになったので助かりました。お昼になると「ごはん、どうする?」とか、まるで夏休み中のような感じでしたね。
鉄道の時刻表を買ってくれたり、「電車、乗りに行こうか?」と声をかけてくれたりしたのも両親です。鉄道は子どものころから好きではあったのですが、不登校期間中に「やっぱり僕は鉄道が好きなんだ」とあらためて気づき、1人でも乗りに行くようになりました。自分で鉄道旅行のプランを立てて、予算まで出せるようになったのもこの時期です。