早稲田大学の田中愛治総長に国際卓越研究大学にかける思いを聞いた。

在野の精神には反しない
――早稲田大学は政府からの独立を謳う「在野の精神」が建学時から尊ばれてきました。国から巨額の支援金をもらう国際卓越研究大学に名乗りを上げることは、この理念に反するのではないでしょうか。
国際卓越研究大学という制度が「在野の精神」に反すると思わない。メディアでは政府が国の言うことを聞く大学を作ろうとしているとよく報じているが逆だ。
文部科学省も内閣府も「政府の補助金に頼らず、独立しろ」「アメリカの私立大学のように基金の運用益などで成長しろ」と言っている。25年間受け取れる支援金をつかって、どう自律するのか自分たちで考えろということだ。
国際卓越研究大学として成長できれば、国が研究分野を定めて公募する研究資金すべてに応募せずとも、独自の研究教育を行うことができる。つまり、支援が終了するまでに基金を拡充し、運用益を伸ばすことができれば建学理念である「学問の独立」と「学問の活用」の精神にのっとった教育研究ができるようになる。

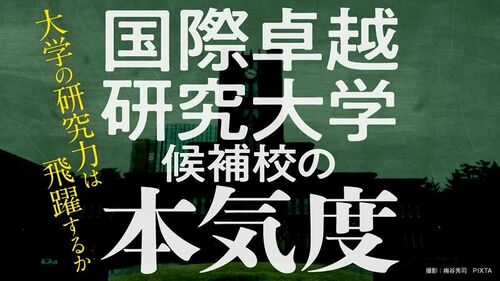
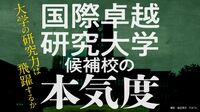































無料会員登録はこちら
ログインはこちら