学校で「なぜ本を読むのか」のサポートが必要、子どもが本嫌いになる3大理由 いかに本を自分の武器として使うかを学ぶべき

元カリスマ書店員の読書教育プログラム
田口幹人さんは、岩手県にある老舗書店チェーン「さわや書店」で、店頭から多くの話題作を世に送り出した出版、書店業界では有名な元カリスマ書店員だ。現在は、合同会社未来読書研究所(以下、未読研)共同代表、NPO法人読書の時間理事長を務めるほか、出版取次会社の楽天ブックスネットワークで少部数卸売りサービス「Foyer」を手がけている。
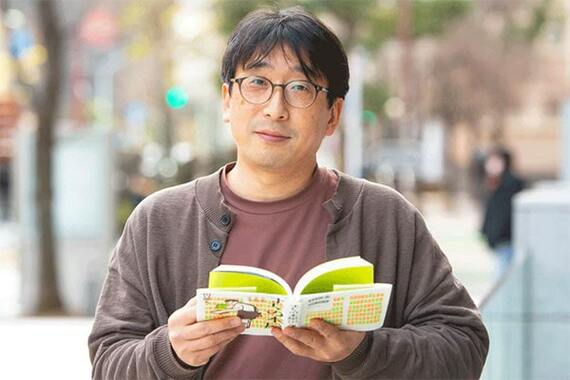
合同会社未来読書研究所 共同代表
1973年岩手県生まれ。盛岡市にある「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。7年半の苦闘の末に店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社し、フェザン店統括店長となる。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに中学校での読書教育や職場体験の中学生の受け入れ、イベントの企画、図書館と書店の協働などを行いつつ、数々の書籍を売り上げ話題となる。2019年に同書店を退社後、合同会社未来読書研究所を設立。2022年にはNPO読書の時間を立ち上げたほか、楽天ブックスネットワーク提供の少部数卸売サービス「Foyer」を手がける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)などがある
(写真:本人提供)
そんな田口さんは書店員時代、1冊でも多くの本を売るためにできることを考える一方、学校や公共図書館で本とのタッチポイントをつくる活動を続けてきた。2019年に未読研を設立したのも、本と出合える場所をつくるためで、子どもたちが本と読書について考えるきっかけとなるよう「読書の時間」という読書教育プログラムも提供している。
出版業界の協力も得ながら、本とは何か、本を読むことの豊かさ、本との出合い方、さらには出版業界の仕事内容まで、本にまつわることを幅広く伝え、未来の読者を育てる取り組みだ。この活動を自治体や地域などと連携しながら拡大するために、昨年立ち上げたのがNPO読書の時間である。こうした田口さんの活動の背景にあるのは、長年いわれてきた子どもたちの読書離れだ。
「私たちは本を読む、読まないではなく、子どもたちになぜ本が嫌いなのかというアンケートを18年前から取り続けてきました。その原因は、おおむね3つに集約されます。3位が『音読で恥をかいた』、2位が『読みたくない本を読まされた』、そして1位が『なぜ本を読まないといけないのかを教えてもらったことがない』。音読は別として、課題図書などで読みたくない本を読まされ、なぜ本を読まなければならないのかを知らないまま、本を読みなさいと大人から言われ続けたら、本を嫌いになるのは当然でしょう。そこで私たちは、この2点について状況を変えようと読書教育プログラムを行っています」






























