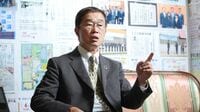世界に後れを取る「メディア情報リテラシー教育」今始めないとマズい訳 求められるデジタル・シティズンシップの視点

従来の「情報モラル教育」では限界がある
GIGAスクール構想の下で1人1台端末が実現し、学校現場でもインターネットを活用する場面は増えているだろう。だがインターネットには、ディスインフォメーション(意図的に作られた偽情報)やミスインフォメーション(勘違いや誤解による誤情報)、マルインフォメーション(攻撃を目的とするなどの悪意ある情報)があふれかえっている。
そんな中、喫緊の課題とされているのがメディアリテラシー教育だ。法政大学キャリアデザイン学部教授の坂本旬氏は、世界の動きについて次のように説明する。

法政大学キャリアデザイン学部教授、図書館司書課程担当。教育系出版社や週刊誌などの編集者を経験したのち、新聞社を中心に雑誌執筆者として活躍。1996年より法政大学教員。ユネスコのメディア情報リテラシー・プログラムの普及を目指すアジア太平洋メディア情報リテラシー教育センターおよび福島ESDコンソーシアム代表。基礎教育保障学会理事
(写真:本人提供)
「例えば、ロシアは膨大な偽情報を組織的にEU各国に向けて発信し、分断をつくっています。EUはこれを重く受け止め、2018年に法改正をしてすべての加盟国にメディアリテラシー教育を行うことと、その成果報告を義務づけました。米国も法律で義務化する州が増えています。これらの民主主義国では、国が情報統制をするのではなく、教育やメディアの自主的な取り組みにより、ディスインフォデミック(偽情報の流行)やプロパガンダに対抗する力を市民が持つことを最優先課題にしているのです」
それに対して、日本は取り組みが遅れていると坂本氏は指摘する。日本では従来、情報への向き合い方に関する教育としては、主に情報モラル教育が行われてきたが、ここには問題点があるという。
「情報モラル教育はインターネット上のリスクを教えるだけで、使用の制限をする教育になっています。しかしそうした怖がらせるアプローチは、例えば米国ではすでに効果がないとされており、どんな危険性があるのかをみんなで議論して考えるような授業をしています。つまり、デジタル時代の市民として責任あるICTの扱いや社会貢献ができるスキル『デジタル・シティズンシップ』の観点でメディアリテラシー教育を行っているのです。日本も、自分にもバイアスがあることを前提に、一歩立ち止まって自ら情報源の真偽を吟味し、クリティカルに読み解いていく訓練が必要です」
ユネスコが掲げる「メディア情報リテラシー」とは?
しかしそんな日本でも、最近ようやく注目すべき動きがあった。2022年6月に総務省が「メディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査結果報告」という報告書を発表したのだ。これは諸外国の状況を分析したうえで、日本における施策の方向性を示したものである。