日本の小学生「丸暗記テスト」が引き起こす学力低下、その「深刻な現状」とは? 子どもの「つまずきを知る」テストに託す希望
また子どもの中には、「14日」の1週間後を、5日後の「19日」と答えた解答例も少なからずあったという。これは1週間を、学校のスケジュールのサイクルである「5日間」と勘違いしていることによるものであると考えられる。
同じ「カレンダー問題」に対する間違いでも、時間の前後を理解できていないために答えを間違った子どもと、1週間を「5日」と捉えているために間違った子どもでは、つまずきの原因は異なり、当然必要となる手立ても変わってくる。
「たつじんテスト」は、上記に挙げた問題例のように、教え手が子どもたちの解答を基に分析することで、何が子どものつまずきの原因なのかを探り出しやすい問題群によって構成されている。
「点数はつけなくていい。子どもの解答を見てほしい」
今井氏らが出版した本のタイトルは『算数文章題が解けない子どもたち』だが、これまで私たちは、算数などの文章題を正確に読み取れない子どもたちのことを、「読解力が足りない」といった評価でひとくくりにしてしまいがちだった。
しかし今井氏は、「読解力がないといっても、なぜ文章を正しく読み解くことができないのか、その原因は子どもによってさまざまであり、『たつじんテスト』の結果を分析していると、そのことがよく見えてくる」と言う。
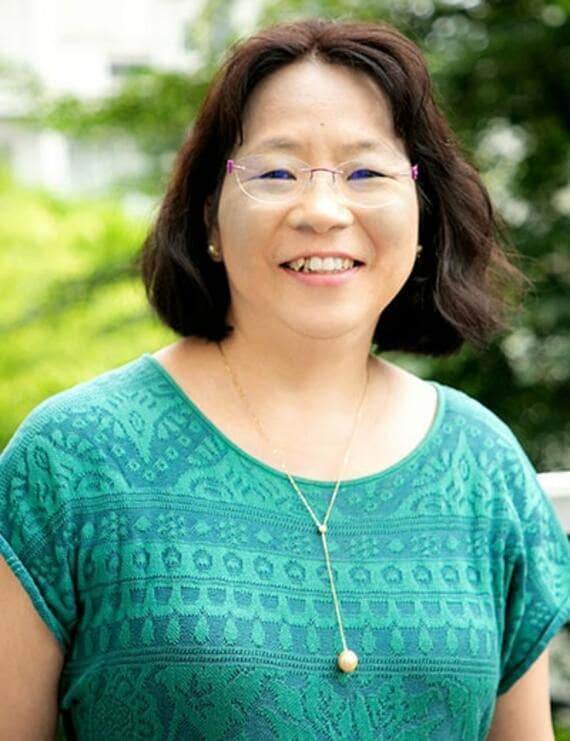
慶應義塾大学環境情報学部教授。専門は認知・言語発達心理学、言語心理学。 平塚江南高校、慶應義塾大学文学部西洋史卒業後、教育心理学に興味を持ち社会学研究科に進学。在学中の1987年より渡米。93年ノースウエスタン大学心理学部博士課程を修了し、94年博士号(Ph. D)を取得。93年より慶應義塾大学環境情報学部助手。 専任講師、助教授を経て2007年より現職。著書に「ことばと思考」「学びとは何か―〈探究人〉になるために」「英語独習法」(すべて岩波新書)、「ことばの発達の謎を解く」(ちくまプリマ―新書)、「言葉を覚えるしくみ―母語から外国語まで」(ちくま学芸文庫)、「親子で育てることば力と思考力」(筑摩書房)などがある
(写真:今井氏提供)
「教科書の文章や、算数など文章題を正しく読み取ることができない理由としていちばん多いのは、やはり語彙力不足です。多くの単語は多義で、複数の意味を持っていますが、子どもによってはそもそもその単語自体を知らない場合もあれば、その単語の代表的な意味しか知らない場合も、確かに多くあります。例えば『切る』という単語であれば、『はさみで紙を切る』『包丁で野菜を切る』といった使われ方については、多くの子どもが理解できています。しかし、『水を切る』という使い方もあり、その意味が『水分を取り去る』ということであるとは、知らない子どもも多い。そうなると、その文章の意味がわからない、そうなってしまうのです」






























