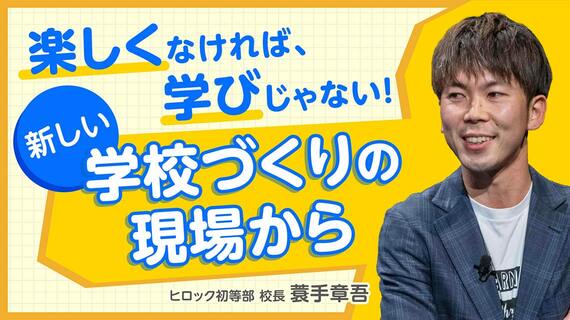日本におけるオルタナティブスクールの課題
日本におけるオルタナティブスクールの課題は、認知度以外にも多くあります。ここでは3つ取り上げてみようと思います。
1つ目は、経済的なスクール維持の難しさ。国の支援を受けられないスクールが多く、人件費や施設維持費は家庭からの学費で賄うしかありません。無料(税金)で通える公立学校に比べると格段にハードルが上がり、生徒を集めるのも難しいのが現状でしょう。
2つ目。大半のオルタナティブスクールは認可外なので、学籍や卒業資格が付与されません。学歴至上社会もだいぶ緩和されてきましたが、それでも不安に感じる保護者が多いこともまた事実です。このあたりのバランスで悩まれているスクールも多いようです。
そして3つ目は、地理的な問題です。ヒロックにも遠くから通ってきている子がいますが、通学を前提とすると、どうしても通える範囲が限られてしまいます。私たちも全国からご相談いただきますが、近場のご家庭のニーズにしか対応できていないのが現状です。
それでも私が、公立学校教員から独立してオルタナティブスクールを立ち上げることにした理由は、教育にもっと選択肢を増やしたいという思いからでした。今の公教育にもすばらしい知見や実践はたくさんありますし、そこで幸せになる力を育んでいる子も多くいます。
一方で、今の学校システムに適応できなかった場合、教育の選択肢の著しく乏しいこの国では、前述したように「不登校≒問題行動」とされてしまう現状があることも事実なのです。私は何も、すべての学校がオルタナティブスクールになればよいなんてまったく思っていませんし、今の公立学校のほうが向いている子もいると思っています。
その中で、せめて1割、オルタナティブスクールが通いやすい形で全国各地に存在していれば、アンテナの高さや経済的なハードルに関係なく、より多くの家庭や子どもたちの選択肢になるはずなんです。
オルタナティブ教育を選択肢として確立することは、今の公教育の子どもたちや保護者だけでなく、先生にとっても働きやすくなるはずだと思っています。先生が自分のやりたい教育で学校を選べるようになるし、多様なニーズをすべて公立学校で受け止めなくてもよくなるからです。入学前に「〇〇のような教育をお望みでしたら、オルタナティブスクールという選択もあるかもしれませんね」という相談が普通にできるようになれば、教育に関わる多くの人たちにとって幸せな世界になると信じています。
(注記のない写真: JGalione / Getty Images)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら