勉強好きな子どもに共通「知的好奇心」、どうすれば伸ばせるか? 「強制せずに」子どもが夢中になる仕掛けとは?

(写真:今井康一)
その特徴は3つある。1つ目はアプリとワークブックで思考力を育てられることだ。同社の算数オリンピック問題制作に携わる教材開発チームが作成した子どもの「地頭」を刺激する問題で、STEAM領域の基礎能力を培うことができる。2つ目はトイ教材で創造力を伸ばすことができること。五感を使って、手を動かす。自分で試行錯誤しながら「こうしたら、どうなるんだろう?」という発想力をトイ教材で引き出していく。3つ目は豊富なテーマで子どもの意欲を高めることだ。バラエティー豊かな教材を通じてさまざまな角度から物事への関心を育み、子どもの知的ワクワク感を引き出していく。新たな挑戦に夢中になることで、学びの原動力がつくられるのである。
「一般的な通信教育は、やはり勉強なので、子どもにやらせること自体が難しい場合もあると聞きますが、ワンダーボックスは知的ワクワク感を引き出す仕掛けが豊富で、子どもが自分からやりたいと思うようになります。今後もより面白い教材を提供することができると考えています」
子どもの知的好奇心を伸ばすことに力を注ぐワンダーラボ。では、日頃から家庭で子どものやる気を引き出すためには何が必要なのだろうか。川島氏が語る。
「まずはやってみてもらう。自分の頭で考えて、間違えることを怖がらせないようにすることが大切です。どんなことに対しても、『無理、苦手、できない』ではなく、『面白そう、楽しそう、できそう』という気持ちを引き出していけるとよいですね。子どもがイライラしているときは何か声がけをするよりも、子どもが達成したことについて、『諦めずに何回も挑戦できたね』など、それまでの過程を意味づけし、親御さんが大事だと思うことを伝えられるとすてきです。そうすれば少しずつ子どもにも伝わっていくのです」
ただ、そこで気をつけなければならないことがあるとも川島氏は言う。
「子どもを結果のみで評価しないことです。結果で評価すると、子どもは敏感なので短期的な結果のみを求めるようになります。同じく、子どもが理解しているかどうかだけを問えば、子どもは理解したふりをするようになる。だからこそ、子どもが楽しんでいるか、試行錯誤しているか、そこを見ることが非常に重要です。これは、家庭でも学校でも同じことです。学びの場が楽しい空間であれば、子どもは大人が予想もしなかったような成長を見せてくれます。そのためにも私たちは、子どもたちが知的にワクワクできる教材を作り続け、多くの家庭に届けていきたいと考えています」
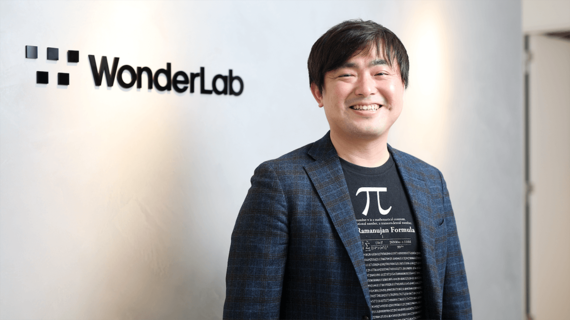
1985年生まれ、栄光学園中・高等学校卒業。東京大学大学院工学系研究科修了。2007年、花まる学習会を運営する、株式会社こうゆうに入社。「なぞぺ〜」シリーズ制作に携わる。4歳から大学生までを教える傍ら、公立小学校や国内外児童養護施設の学習支援を多数手がけ、14年、ワンダーラボ(当時、花まるラボ)を設立。開発した思考力育成アプリ「シンクシンク」は世界150カ国200万ユーザー(2020年1月現在)、「Google Play Awards」など、国内外で受賞多数。世界中の子どもたちから「知的なワクワク」を引き出すことをミッションとし、アプリや書籍、知育玩具など、多様なコンテンツを生み出している。過去に、東京大学非常勤講師を務めたほか、毎年算数オリンピックの問題制作に携わり、17年より三重県数学的思考力育成アドバイザーも務める
(写真:今井康一)






























