右肩上がりで成長しているとはいえ、日本のM&A市場は世界的に見て遅れており、M&Aマフィアに対するニーズは今後も高まりそうだ。

「日本のM&Aは欧米に比べて20年は遅れている。だから投資ファンドやアクティビストなど欧米勢のやりたいようにやられている」
ある投資ファンドの幹部は、日本のM&Aの現状に関してそのように指摘する。
事実、英金融情報会社のリフィニティブによれば、2021年の世界のM&A総額は、過去最高の673兆円。うち米国が428兆円と6割超を占めている一方、日本は増加こそしているものの20兆円に届かないレベルで、圧倒的な差が生まれている。
背景としてはもちろん企業の時価総額の違いもあるが、M&Aの歴史によるところが大きい。
米国でM&Aが生まれたのは1900年代前半のこと。70年代に入って本格化し、企業はM&Aにより規模の拡大を追求した。しかし80年代に入ると、肥大化した企業の効率性が問題視されるようになり事業売却が増加。短期間のうちに買収と売却を経験したことで、M&Aが定着したといわれる。



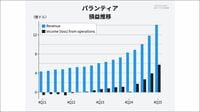





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら