はやり廃りはあるが、王道は昔も今も現金と利益の差だ。

危うい会社を見分けるコツは何か。独自の会計分析を基にRIZAPグループ(以下ライザップ)やZOZOの危機を見抜いた細野祐二氏に聞いた。

いわゆる粉飾決算やいかがわしい会計処理には、はやり廃りがあります。私も長いことやっているので、時代によって粉飾決算もいろいろな歴史を経てきたとしみじみ思います。
財務分析上、危うい会社を発見する1つ目の切り口は国際会計基準(IFRS)と日本基準の差です。伝統的に粉飾決算は、実際には出てもいない利益を計上するわけです。ということは、粉飾企業は払わなくてもいい税金を払ってきた。したがって、伝統的な粉飾は長期間継続することができない。税金としてキャッシュアウトするから長期は無理なのです。粉飾はやれても1期か2期。それ以上やっていくと資金繰りが行き詰まるからほぼばれるというのが、粉飾決算の定説でした。すなわち、税務が粉飾の大きな抑止力になっていたのです。
ところが、IFRSが出てきて以降、その税務が抑止力にならなくなりました。なぜかというと、税務はあくまでも個別決算に基づいて申告をする。そして個別税務計算は日本基準です。





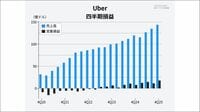





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら