
敵失に助けられ勝利
蒙古襲来は、前近代において日本が体験した外国からの侵略戦争で最大のものである。
文永の役(ぶんえいのえき)(1274年)、弘安の役(こうあんのえき)(81年)と2回にわたり、蒙古軍が九州北部と一部は長門(ながと)(山口県)に上陸した。だが日本は蒙古軍を撃退した。この勝利について、のちに嵐によるものと認識され、嵐は「神風」と称されるようになった。神風は太平洋戦争中は戦意高揚の象徴にもなった。
確かに二度とも嵐はあったし、戦闘に影響している。では嵐による影響はどの程度だったのか。冷静になって本質を検討したい。
まず文永の役。この戦での嵐は台風ではない。文永の役で博多合戦があったのは現代の暦では11月下旬。この季節に九州北部に台風が来ることはない。この季節は寒冷前線が通過する。海が荒れ、現代でも東シナ海や日本海で沈没事故がしばしばある。
文永の役では、これまでの通説により、蒙古軍は1日で帰ったと信じられている。しかし外国遠征軍が、負けてもいないのに1日だけで帰るだろうか。

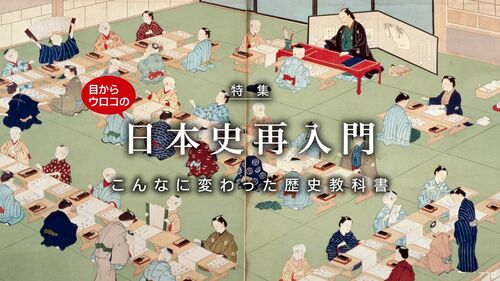































無料会員登録はこちら
ログインはこちら