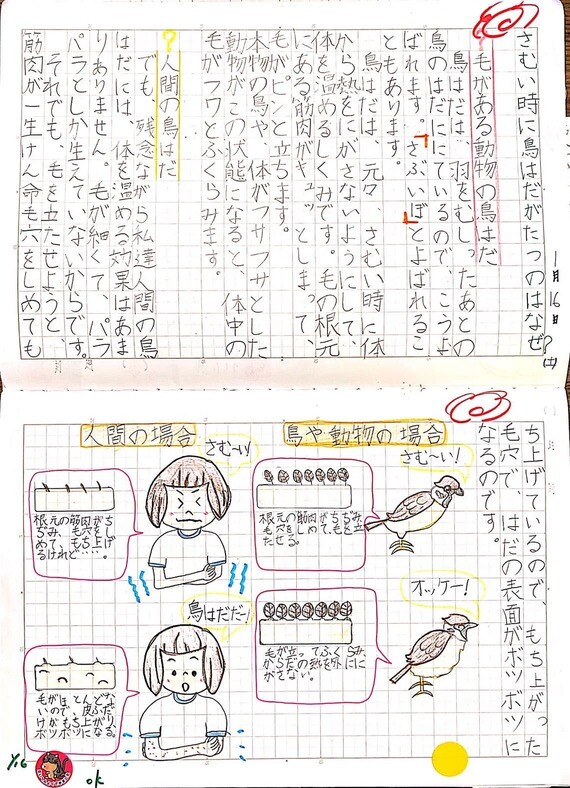
(写真:田中氏提供)
今のクラスでは、自主学習ノートに加え、1つのテーマをひたすら深掘りする「探究学習ノート」に挑戦する子もいて、すでに1冊終わった子が4人います。探究のテーマは、沖縄県、京都、猫、忍者、ポケモンなど、各自が好きなものや興味のあるもの。教員は教科学習と絡めたがりますが、楽しいものでいいのです。社会人になるとリポートを書いたりプレゼンテーションしたりする機会が増えますが、自由に探究する中でそういった将来必要な力が養われると考えています。
また、クラスの様子を見ながら、毎日帰りの時間や給食を食べた後などの隙間時間を使い、「家に帰ったら何をどのくらいの時間やるか」を自分で決めるよう促します。大人になるとセルフマネジメントやタイムマネジメントが大事になるので、ゴールや時間、クオリティーの設定をあらかじめ決めて実行し、振り返るという作業を意識させるのです。こうしたマネジメント力も自主学習ノートで培えると思っています。
――そのほか、どのような力が身に付くと感じていますか。
毎週の漢字テストの合格者数が増加するなど、やはり家庭学習が「当たり前」になると感じますね。日常的に調べる機会が増えるので、辞書や事典、資料集、計算機、パソコンなどのリサーチツールを使いこなせるようにもなります。
また、自分でテーマを決められるようになったり、「今日は習い事があるからこのくらいの分量にしよう」「今日は背伸びして頑張ってみよう」といった配分のコントロールもできるようになったり、自分で「選択」「決定」する力が身に付くようになります。そういった自分に合った学び方の模索を通して、学習に前向きになるという効果もあるように思います。

1978年生まれ、北海道出身。東京都の公立小学校教員として14年間勤務。2016年、主に病気休職の教員の代わりに担任を務める「フリーランスティーチャー」となる。これまで公立・私立合わせて延べ11校で講師を務める。NPO法人「Growmate」理事としてマーシャル諸島で私設図書館建設にも携わる。近著に『マンガでわかる!小学校の学級経営 クラスにわくわくがあふれるアイデア60』(明治図書)
(写真:田中氏提供)
(文:編集チーム 佐藤ちひろ、注記のない写真はiStock)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































