「イタズラする犬」のストレス耐性を育てる技術 「小さな経験」を積み重ねることが重要
先程のコンセントのプラグの話でいえば、「感電するのでプラグをかじるのはダメ」というルールを作るのは、人と犬が共生するうえで適切なルールですが、極端にいえば、そもそもそんな家に住んでいる人は動物を飼ってはいけないということもいえるかもしれません。動物目線だけで考えれば、コンセントが家にないなら制限を受けなくて済むので、動物にとってはフェアかもしれません。
しかし、現実には、人が犬を飼いたいという気持ちがまずあって、それを満たす形で、人の家に犬を住まわせています。
いわば人の勝手で犬を飼っているわけで、都会のマンション住まいの人から田舎に広大な土地をもっている人まで、家にずっといられる人から留守になりがちな人まで、さまざまな状況下の人が、犬を飼育動物として利用することを前提に、犬を迎えています。
さまざまな状況のなか、犬にとってのベストは必ずしも実現しません。大切なのは、それぞれの状況下でできるだけ犬にフェアな飼育環境を提供する努力をするということです。
人と犬、双方にフェアなルールを
しかし、攻撃行動がある犬の場合、できる限り犬にフェアにするということすらままならないことがあります。飼い主や家族の安全確保が優先されるからです。
小さな嫌悪刺激(リードの付け替えなど)に対しても、攻撃行動を取る場合、飼い主と犬が共生していくうえでは、双方の不快やストレスをどうやって調整し、生活を成り立たせるかを考える必要が出てきます。
犬にとっての不快をすべて避けようとすれば、散歩に行けなくなります。散歩をしないことは、犬にフェアとは言い難く、むしろストレスになります。
結果、リードを付けっぱなしにするという対応になるわけですが、それも犬にとっては不快になるかもしれません。攻撃行動のある状況では、犬がまったく自由に生活するということは考えづらく、何らかの制限下で生活させることになります。
できるだけ犬にフェアであろうとする時にどんなルールを設定するかは、飼い主と犬の置かれた状況によって異なります。大切なことは、人は学ぶことができ、新たな行動を率先して選択することができるという点です。
できるだけ犬のことを学び、専門家の助けを借りたうえで、どうやってこの犬と付き合っていくか、どの部分で制限し、どの部分で発散させるか、考えていかなければなりません。
人と動物の共生に関する知識を十分に得て、人と犬、双方にフェアなルールを飼い主が責任をもって決めていくという姿勢こそが、犬を飼ううえでの倫理観といえるでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

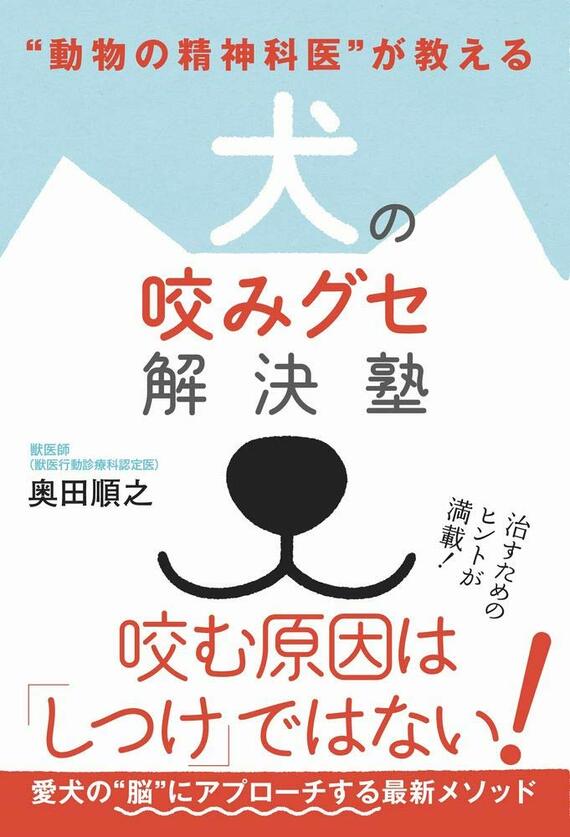






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら