日本人はなぜ「桜」をこんなにも愛するのか 「散り際」に美を感じるのは本来ではない?
奈良時代から平安時代になって日本人の好みが変わったのではおそらくなく、桜が好きであることは変わらないのです。ただ、飛鳥時代に海の向こうから渡来した文明の摂取に懸命となっていたので、海の向こうのものはなんでも尊いと思うしかなかったのでしょう。あたかも明治の御一新で西洋崇拝に陥り、金髪碧眼ワンダフルとなったのと同じですね。
桜のどこに美しさを感じますか? 「花は桜木、人は武士」という言葉があります。武士の潔さは死に際にあり、桜もまた散り際が見事であるから美しいとされるのが通説です。ただ、これが本当だとは思えません。
桜の美しさをうたった歌の白眉は本居宣長の「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」だと思います。戦前戦中の人でこの歌を知らない人はいません。この歌は国のために強いられた死で散った、多くの若者を悼むものとして記憶されています。まさに「歌書よりも軍書に悲し吉野山」だったのです。
散華(さんげ)という語は、辞書で引いてみると「仏を供養するために花を散布すること、またその花」とありますが、末尾に「誤って、華と散ると解し、戦死を指していう」という語義が載っています(『広辞苑』)。人々は若くして散った命を哀惜して、誤用を自覚しつつ死を美しく飾るために使ったのでしょう。けれど、散華が陶酔を呼び覚まし、戦意高揚につながったことも否定できません。
ただ、宣長の込めた意味は違います。『玉勝間』の中で「花はさくら。桜は山桜の葉赤くてりてほそきが、まばらにまじりて、花しげく咲きたるは、またたぐふべき物もなく、うき世のものとも思はれず」と書き、花の散り際には触れずに、満開こそ美しく、敷島の歌も「ただうるはしい」と述べています。
朝日に照り映えて咲きほこる山桜の美しさこそ、日本人の心なのです。花は咲いてこそ花であり、花の美しさを表現することができます。人間も生きて生き抜いてこそ、他者と協働して自らのレゾンデートルを発揮できると思われるのです。散るのが美しいとすれば、生き抜いてこそなのです。
そして、美しさは力となります。梶井基次郎は「桜の樹の下には屍体が埋まっている」と書きました。桜が狂気なのではない、桜の美しさが度を超しているのです。ナイーブな感受性は、美しさにおののき狼狽します。
ここにおいて美は力に転じ、暴力性をも有することとなります。なんとセンシュアルなことでしょうか。美しいがゆえに強い、これが大和心すなわち日本人の心なのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

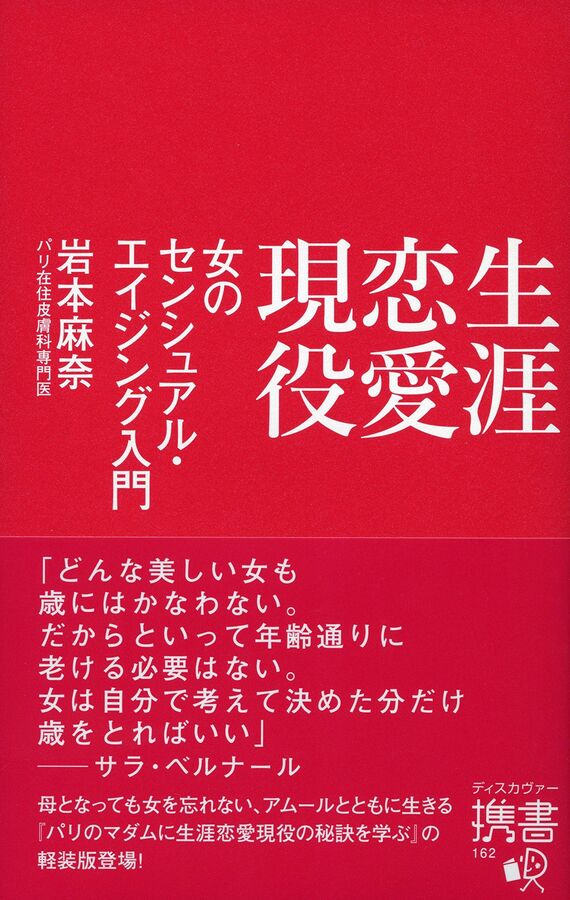






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら