今さら聞けない「確定拠出年金」基本中の基本 その仕組みを知って老後資金対策を考えよう
資産運用は運用する期間が長ければ長いほど、複利の力を享受できるので、確定拠出年金への加入時期が早ければ早いほど、そのメリットの恩恵が大きくなります。
受け取り時にも大きな税制優遇
確定拠出年金は60歳まで積立し、60歳以降70歳までの任意の期間内に一時金で受け取るか、もしくは年金として分割して受け取るか、もしくは両方を組み合わせて受け取るかを選択できるのですが、いずれの場合にしても税制優遇が大きいのです。
一時金として受け取る場合、退職所得控除が適用されます。これは加入期間1年について40万円の控除枠が認められます。しかも加入期間が20年を超えると1年あたり70万円の控除枠が認められ、さらに控除しきれなかった金額の半額が課税対象となります。
たとえば、確定拠出年金で月2万円の積立を30年継続したとしましょう。すると、元本だけで720万円の自分年金をつくることができます。その資金を60歳で一時金として受け取るときの退職所得控除は1500万円(40万円×20年+70万円×10年)ですから税金を引かれることなく全額自分のおカネとして受け取れます。
また、年金として受け取る場合は、公的年金控除としての優遇がありますので、他の金融商品あるいは金融の仕組みと比較しても、確定拠出年金は老後資金づくりに有利だといえます。
会社員で会社に厚生年金基金などがない人や自営業者は確定拠出年金個人型の加入資格があります。ただし加入資格は60歳までなのでタイムリミットがあることにも注意です。
確定拠出年金にもデメリットがあります。それは、確定拠出年金はあくまで年金なので、60歳まではいっさいおカネを引き出せないという点です。ですから、確定拠出年金の掛金を決める際には、節税になるからといって上限いっぱいの掛金を設定すると、手元に必要なおカネが残らないという思わぬ落とし穴にハマってしまうかもしれません。
おカネは3つに分けて考える
では、掛金をいくらにすればいいでしょうか?おカネは目的別に「使うおカネ」「貯めるおカネ」「増やすおカネ」と3つに分けます。いま手元にあるおカネを3つの箱に分別して、これから貯めるおカネもそれぞれの箱の中でつくっていくというイメージです。
「使うおカネ」の箱は、いつでも使えるようにしておく必要があります。
「貯めるおカネ」の箱は、5年から10年以内に使う目的のおカネを入れます。
「増やすおカネ」の箱は、10年以上先に使う目的のおカネ、あるいはまだ用途が決まっていないおカネを入れます。
「使うおカネ」は、日々出し入れしやすいように銀行の普通預金口座においておきます。非常事態があってもあわてることがないように、基本的な生活費の3カ月分くらいあるといいかと思います。給与が振り込まれる口座を「使うおカネ」にするのが、一番いいでしょうね。




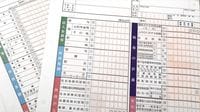


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら