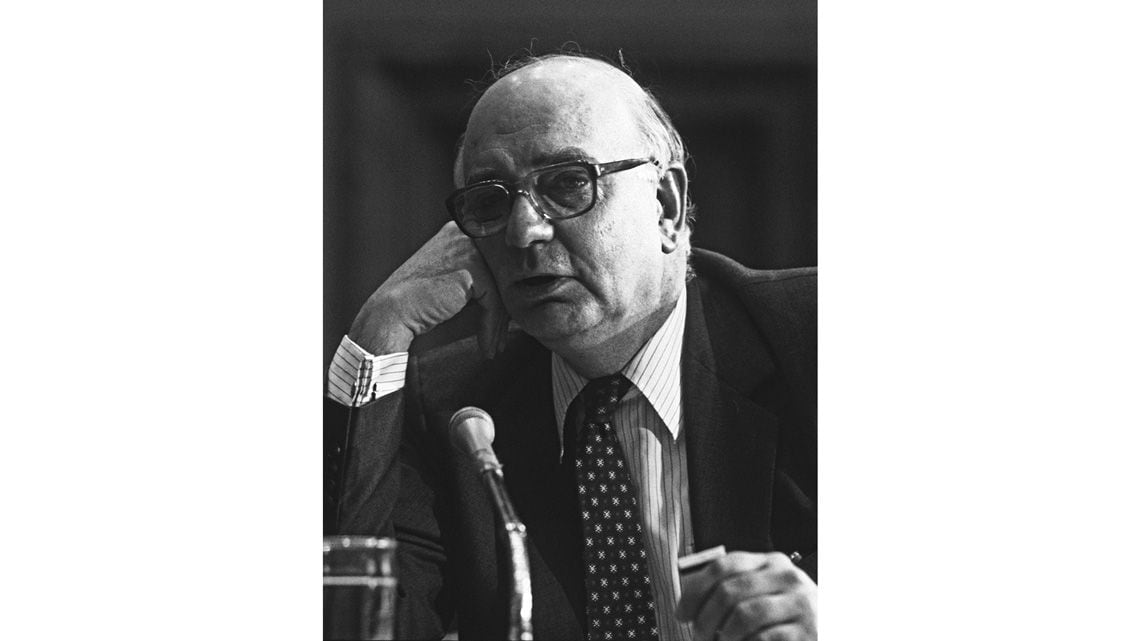
1985年9月のプラザ合意から3カ月が過ぎ、円相場は1ドル=240円台から200円に上昇した。景気は前年6月にピークアウトし減速していた。
当時大蔵省国際金融局長だった行天豊雄は、オーラルヒストリーで、この間の「世論の変化」を次のように振り返っている。
「ドル高円安が改善され、これで貿易黒字も減って対日批判も減るだろう、よくやった、万歳という感じが(当初は)あったわけですけれども、こういう戦勝ムードは急速に消え去り、もう年末には本当に大丈夫かな、この調子で今度は逆に円高が進んで大丈夫かなというふうに変わっておりました」
事実、日本銀行総裁の澄田智が短期金利の高め誘導を解除すると表明した12月18日、首相の中曽根康弘は「金利低下を日米協調で実現する時期がきている。金利下げはわが国の内需拡大に大切」と公定歩合の引き下げを催促した(85年12月18日付「日本経済新聞」)。急激な円高・ドル安への警戒感が広がり始めていたのだ。


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら