企業や起業家と連携、興味を探究してキャリアにつなげる「通信制サポート校」ができた訳 HR高等学院「社会との接続」で課題解決力を育成
同校で特別顧問を務める東京学芸大学教育インキュベーションセンター長の金子嘉宏氏も、サポート校の必要性を感じている。
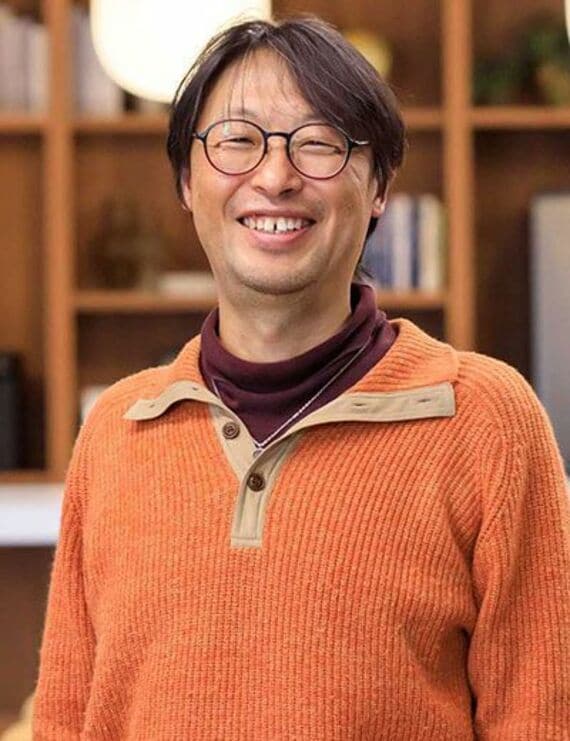
HR高等学院特別顧問
東京学芸大学教育インキュベーションセンター長教授。専門は社会心理学、教育支援協働学。「遊び」についての産学共同研究を数多く実施。新しい学びの場の創造プロジェクト「Explayground」、学校の変革プロジェクト「未来の学校みんなで創ろう。PROJECT」等の実践事業やSTEAM教育の推進等に取り組んでいる
「学校は世の中に出たときに必要となることを教えます。それが公教育ですが、学習内容はある程度決まっており、必ずしも子どもたちにとって興味のあるものではありません。子どもたちが主体的に学びたいことへのサポートが、どうしても薄くなる仕組みになっています」(金子氏)
高校では総合的な探究の時間が設けられたが、それだけでは時間が足りないという。「子どもたちが本当にやりたいことを支援してあげる場所が、学校以外に必要だと思います」と、金子氏は話す。
また、これまでの学校教育は“知る”がベースだったが、今の社会では得た知識を活用して新たな価値を創造することにつなげることが求められている。
「問題解決できる人材が必要となる中、学校教育だけでは価値創造的な学びのフォローは難しい。HR高等学院は、まさにその役割を果たせるのではないでしょうか」(金子氏)
「探究」や「現代的教養」で個別最適な学びを提供
HR高等学院はサポート校のため、生徒は提携先の鹿島山北高等学校に在籍する。午前中は高校卒業資格取得に向けた基礎教科を学習し、午後からHR高等学院ならではの多様な学びに触れることができる。

では、数あるサポート校の中でも、どのような特徴があるのだろうか。
「多くのサポート校は、大学受験を支援する授業や子どもたちのサードプレイスとしての役割を担うことがメインだと思います。HR高等学院ではそれだけでなく、はたらく部のノウハウと金子さんの知見を掛け合わせた探究的な学びや、将来プロジェクトを牽引できる経験や知識が身に付く現代的教養を提供する予定です。学びの領域としては、ビジネス&アントレプレナーシップ、テクノロジー、デザイン、ソーシャル、グローバルを用意。これだけ幅広く選べるサポート校は珍しいと思います。生徒はそこから興味のある分野を見つけて、実践プログラムや専門ゼミを体験。テクノロジーが『違う』と思ったらデザインにいってもいいし、いきなりゼミに入ってもいい。個別最適なカリキュラムを組むことができ、それに合わせたきめ細かな個別サポートも実施します」(山本氏)































