認知度も低下、教員の処遇改善…教育の重要局面で何ができるか?「日教組」の現在地 過去最低の組織率18.8%でも発信強化の真意
校長が逮捕されるような事態を望んでいるわけではありませんが、そういう強い力が働かないと変わらないのではないかと思います。地公法第58条を改正して、強い権限をもった労基署が監督権を行使できるようにすることにより、教職員のいのちと健康が守られるという労働者として当然の権利を、私たちは求めていきたいと思っています。
——日教組の組織率が2024年10月時点で18.8%と過去最低、しかも48年連続の低下となっています。その原因と対策について教えてください。
認知度が上がっていないことに原因があると認識しています。この状況を変えるためにも、さらに情報発信を強化していかなければいけないと考えています。
たしかに学校現場は過酷な状況にありますが、産休に育休、少人数学級、それに学校5日制など、日教組が地道に訴えてきて実現したものも多くあります。ただ実現までに時間がかかっているのは仕方のないことで、学校5日制は日教組が方針化してから学習指導要領の改訂で実現するのに30年かかりました。教員免許更新制度の廃止も、方針化してから13年かかっています。その間、私たちが全国で連帯して繰り返し繰り返し訴えて、それで実現したわけです。
時間のかかる地道な訴えをしてきている私たちの活動が認知されにくくなっているのも事実です。そうした地道な活動をしていることを、もっと積極的に発信して、認知度を上げていくことが必要だと思います。
——受け取り手の問題もあると思いますが、日教組は何を目指しているか理解されていません。「賃上げ」なら一部の組合員に任せて、自分はかかわりあいたくない、と思っている若い教員も少なくないように思います。
賃金だけでなく、先ほども言ったように、少人数学級や学校5日制、さらにインクルーシブな学校づくりなど、すべての子どもたちのゆたかな学びの保障に、日教組は取り組んでいます。日教組が主催する教育研究全国集会で理想の学校について全国の仲間と議論することは、自身の視野を広げる意味でも貴重な体験になるはずです。日教組に加入することで、子どもにとっても教職員にとっても居心地のいい学校を実現できると理解してもらえれば、多くの教職員に振り向いてもらえるはずです。
私が中央執行委員長に就任した1年前は、日教組が結成されてから77年にあたるときでした。あと23年で結成100周年を迎えるわけです。
就任にあたっての挨拶で私は、「この100周年のときに、全国すべての学校で、日教組が目指す『子どもたちのゆたかな学び』が実現できるよう、これまでの運動を継承しつつ種をまいていきたい」と述べました。その「ゆたかな学び」に向けた運動と未来のための種を、目に見えるものとして示すことができれば、「こんな学校を日教組と一緒に実現したい」と思ってくれる教職員が増え、組織率も上がっていくと期待しています。そのためにも、情報発信の強化に取り組んでいきます。
(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)
執筆:フリージャーナリスト 前屋毅
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

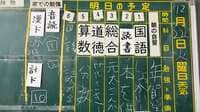





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら