日銀の対話手法は、「金融政策は政策委員会が決める」というルールを厳格に守っている、と言えるだろう。「説明責任」と「透明性」を重視した改正日銀法の趣旨にも沿ったものだ。
だが、タイミングの不明な利上げ方針の下、「決めたことしか言わない」のは、金融市場にとって利上げの円滑な織り込みは難しい。昨年7月末の利上げは、日経平均株価の暴落を招いたが、今後も同様のショックを招く恐れがある。
定番の示唆用語にはできない悩ましさ
今回の利上げは、氷見野副総裁と植田総裁の「利上げを議論する」とのフレーズが結果的に利上げ示唆となり、金融市場の混乱を招かずに済んだ。
日銀にとって悩ましいのは、次の利上げに際し、事前に「利上げを議論する」とのフレーズを使うかどうかだ。使えば、金融市場はただちに織り込むだろう。だが、示唆用語として定着すると「政策委員会が決める」というルールの軽視となる。簡単には使えないわけだ。
このことは、今後の利上げ路線において、日銀の「コミュ障」的な対話が続くことを意味する。
過去2回の利上げを経て、「半年に1回」が正常化のペースとみられる。次のタイミングは夏だが、それに向けてうまく対話できるかどうかは予断を許さない。何の示唆もなく追加利上げすると、金融市場の混乱は避けられないだろう。
対話のルール厳守か、金融市場の安定か。どちらを重視するのか、「コミュ障」日銀のジレンマは続く。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら








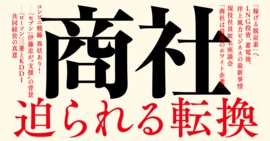





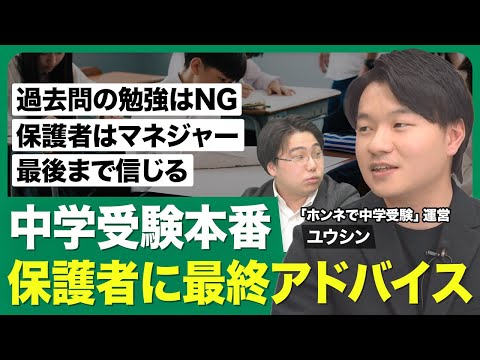





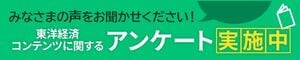
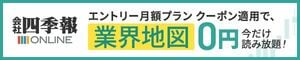
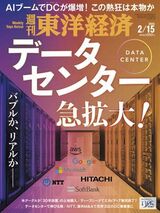







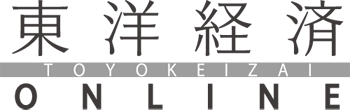


無料会員登録はこちら
ログインはこちら