これに対し、米連邦準備制度理事会(FRB)は、パウエル議長が先々の金融政策運営を具体的に語るほか、連邦公開市場委員会(FOMC)の声明では、先行きの政策金利見通しが示される。金利見通しは、確定したものではなく、あくまでも参考程度だが、金融政策の先行きはイメージできる。
日銀もそうすればいい、と思うかもしれないが、ここでネックとなるのが、日銀の対話手法はかなり自由度が乏しいことだ。
議論して決まるものだから事前に語れない
日銀が事前に金融政策の行方を語らない理由について、氷見野副総裁は前述の挨拶で次のように説明している。
「毎回の金融政策決定会合の結論を事前に市場に完全に織り込んでもらえるコミュニケーションをとるべきだ、とはならない。(なぜなら)金融政策は毎回の政策委員の議論で決めるものであり、そのようなこと(事前に語ること)は不可能だ」。
決まってもいないことを語ることはできない、というスタンスなのだ。
これは1998年に施行された改正日銀法における日銀の基本方針だ。この法改正で日銀は「説明責任」と「透明性」を重視した。金融政策は政策委員会で議論して決める。議長(総裁)が言えるのは、決定した内容の説明にとどまる。決めてもいない先々の政策に言及するのは政策委員会の軽視となる。さらに「説明としても無責任であり、透明性を欠く」(日銀OB)ことになる。
このほか、利上げをする、しないのスタンスがブレやすいのは、植田総裁の「丁寧な説明」が影響している面もあろう。
総裁会見を振り返ると、利上げする理由、しない(=現状維持する)理由をそれぞれ詳しく、丁寧に説明する印象が強い。詳しい説明は、金融市場に対して多くのヘッドラインが流れる。利上げの理由が多く流れると「タカ派の印象を強める」(別の運用会社エコノミスト)一方、利上げしない際には逆に「ハト派の印象を強める」(同)わけだ。








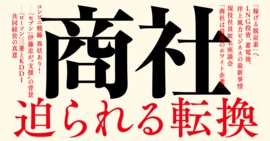





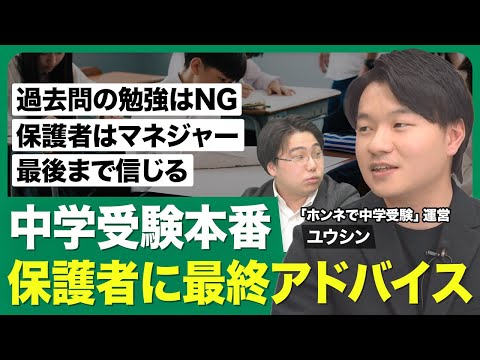





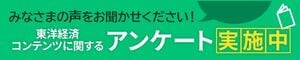
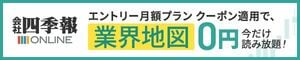
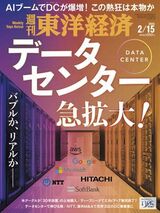







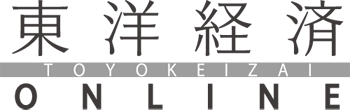


無料会員登録はこちら
ログインはこちら