利上げに前向きな姿勢をタカ派、慎重姿勢をハト派とすると、昨年12月初旬からの情報発信はタカ派、ハト派のそれぞれの方向で大きく揺れ動いた。
もとより、日銀は意図してタカ派と、ハト派を演じ分け、金融市場を動揺させているわけではない。日銀としては丁寧な情報発信を心掛け、金融市場が利上げを自然な形で織り込んでほしい、と願っている。
残念ながら、いくつかの要因によって「対話」がうまくいかない状況を招いている。大きな要因を2つ挙げるなら、「利上げ路線自体がわかりにくい」こと、そして「対話の自由度が乏しい」ことであろう。
「いつやるか」は日銀の「決め」
日銀が進めている利上げ路線は「金融緩和の度合いを緩める」というものだ。経済に中立的とみられる水準まで政策金利を引き上げるわけだ。
緩和度を緩めるだけならいつでもできる。厄介なのは、部外者には「いつでもできるものは、いつ実行されるか、そのタイミングがわからない」ことだ。利上げする、しないは、日銀の「決めの問題」であり、金融市場には「決め」という日銀心理を察知する超能力はない。
日銀は「中立金利の推計にはかなりの幅がある」(幹部)として水準を具体的には示していない。2%の物価目標を達成する確度が高まれば「金融緩和の度合いを調整する」(展望リポート)としているが、調整タイミングのメドに言及するわけでもない。
金融市場には「利上げのタイミングと政策金利の終着点(中立金利)はさっぱりわからない」(運用会社エコノミスト)のだ。








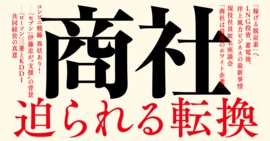





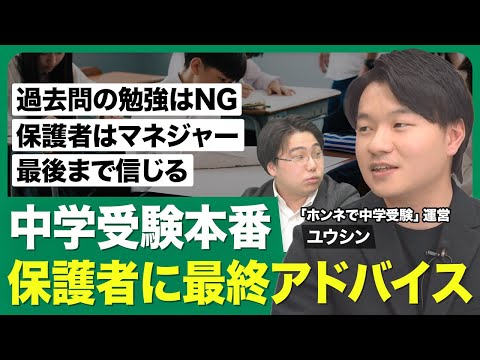





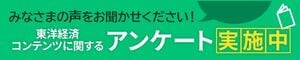
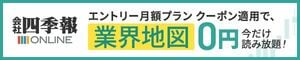
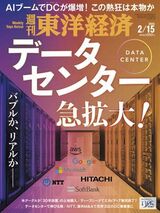







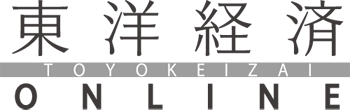


無料会員登録はこちら
ログインはこちら