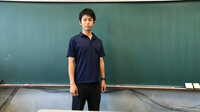学級経営の危機「6月」目前、規律やルールだけではNG「クラスの荒れ」への対処法 教室の秩序形成に必要な教師と子どもの関係性

いじめが増える時期は6月と11月
学級経営には、これまで実践的に3回の危機があると言われてきました。6月、11月、そして2月です。先生方の実感としてはいかがでしょうか。「あるある」と賛同する方もいれば、「それはどうかな」と懐疑的な方もいることでしょう。
脳科学者の中野信子氏は著書『ヒトは「いじめ」をやめられない』(小学館新書)の中で、いじめが増える時期は6月と11月だと指摘し、注目を集めました。
安心ホルモンであるセロトニンの分泌や合成が、日照時間などの変化によって5月から6月、10月から11月にうまくいかなくなり、その結果、不安が強まりうつ状態を経験しやすくなると言います。セロトニン不足は、不安を強めるだけでなく、暴力性が高くなるなどの傾向があるのだそうです。
学校現場では、どのようなことが起こっているでしょう。数は多くありませんが月別にいじめの認知件数をまとめた自治体のデータを調べてみると、6月と11月に大きな山、そしてそれらに比して小さなものですが、2月にも山が確認できました。
学校における月別の負傷や疾病の件数も、小中高等学校いずれも6月、11月、そして2月に多くなっていました(独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校等の管理下の災害 [令和5年版] 令和4(2022)年度データ』2023)。6月、11月の学校は、研究授業や行事なども盛んになってきて、ただでさえ慌ただしい状況であることは学校現場で働いたことがある方ならご存じのことでしょう。
この時期は生物的、個人的要因だけでなく、環境的、社会的要因も重なって、怪我や病気だけでなく、人間関係上のトラブルも起こりやすくなっているのかもしれません。学級が、この時期に荒れたり不安定になったりする可能性があることは、知っておいてよいのではないでしょうか。
学級が荒れるのは必要なことを「知らない」だけ?
学級が荒れると「自分には力がないから」と考える方がいますが、それは資質とか能力の問題ではなく、必要なことを「知らないから」かもしれません。
教科指導にも基礎や基本があるように学級経営にも基礎や基本があります。教室は教師と子ども、また子ども同士の個別の物語の絡み合いですから、十把一絡げに捉えることができませんが、やはりそこは人と人の営みが成り立つための必要条件や前提条件があろうかと思います。

国立大学法人上越教育大学教職大学院教授
19年の小学校勤務を経て2008年4月より現職。現在は、教員養成にかかわりながら小中学校の教育活動改善支援、講演、執筆活動をしている。学校心理士、日本授業UD学会理事、日本学級経営学会共同代表理事、NPO法人全国初等教育研究会(JEES)理事。『指導力のある学級担任がやっているたったひとつのこと』『アドラー心理学で変わる学級経営』『学級経営大全』『明日も行きたい教室づくり クラス会議で育てる心理的安全性』(いずれも明治図書出版)、『赤坂版「クラス会議」完全マニュアル 人とつながって生きる子どもを育てる』(ほんの森出版)など著書多数
(写真:赤坂氏提供)