いじめや授業の議論とも関連、教員は「スクールカースト」をどう考えるべきか 「学校適応感」や「学校享受感」との関連も大きい

スクールカーストの地位が「学校の楽しさと」強く関係
文部科学省の「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、いじめの認知件数・重大事態件数が過去最多を更新した。いじめの背景はさまざまだが、以前から「スクールカースト」は、その要因の1つになっているとの指摘がある。
スクールカーストとは、学級の児童生徒間や集団間で、自然に発生する固定的な序列を指す概念で、インドの階級的な身分制度であるカーストになぞらえて名付けられたといわれている。スクールカーストを心理学的アプローチから研究している北海道教育大学旭川校准教授の水野君平氏は、次のように話す。
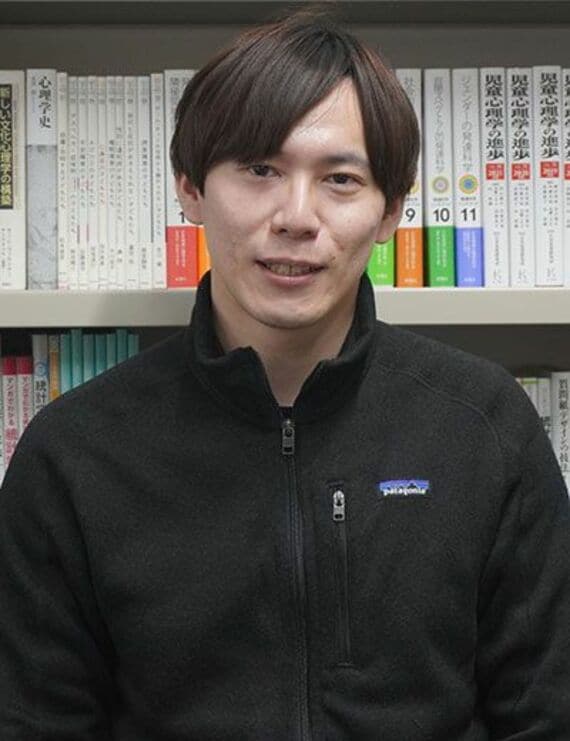
北海道教育大学旭川校准教授
2019年に北海道大学大学院教育学院で博士(教育学)を取得した後、北海道大学環境健康科学研究教育センター学術研究員、De Montfort University Academic visitor。2020年に講師として北海道教育大学旭川校に着任し、2023年より現職。旭川市スクールカウンセラー、旭川市いじめ防止等連絡協議会会長などを兼任。専門はいじめや学校適応などの生徒指導領域に関する心理学的研究。公認心理師。共著に『あなたの経験とつながる教育心理学』(ミネルヴァ書房)、『はじめての発達心理学』(ナカニシヤ出版)など
(写真:水野氏提供)
「そもそもこの言葉は、2000年代前半にネット上で生まれたようですが、2007年に刊行された教育評論家・森口朗氏の著書『いじめの構造』(新潮新書)を通じて社会的に認知が広がりました。森口氏はスクールカーストを、子どものコミュニケーション能力によって序列が決まり、個人間の序列を表わすものと定義していますが、グループ間の序列を指すこともあり、定義は研究者によってもさまざま。ですが、共通して、学校や学級の中で上下関係のような地位の差が生まれることを意味します」
































