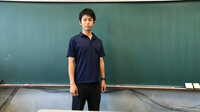1年の始まり「4月の学級経営」で大事なこと、バックキャスト思考のススメ 問題起こることを前提にベターな学級づくりを

「バックキャスト思考」が学級経営のヒントに
2024年度が始まりました。多くの先生方が、子どもたちの健やかな成長を願って教育活動を始めていると思います。
ただ、1年以上にわたる学級生活では、子どもの問題行動や保護者からのクレームなど予期せぬ事態によって揺さぶられ、思いの実現や目標の達成がままならないこともあります。あれをしたい、こうしたいと思った4月とは対照的に、充実感とは程遠い感覚に包まれた3月を迎えることもあるでしょう。
多様な子どもや保護者のニーズに応えながらも学級を教育の場として機能させていくにはどうしたらいいのでしょうか。そんなときにヒントになるのが、バックキャスト思考です。
未来から逆算して目標や計画を立てる思考法で、SDGsの策定や環境問題の解決において注目されましたが、目標達成の発想法としては以前から知られていました。授業づくりにおいても、何がどれだけいつまでにできればいいかといった期待する成果、つまり達成すべき目標をまず決めて、展開や導入を決める「逆向き設計」の授業づくりとして実践されています。
バックキャスト思考は、長期的かつ達成が難しい課題に強いとされています。学級経営は、取り組みの内容が多岐に及ぶうえに学校や地域、校種によっては1〜3年にわたる長期にわたる取り組みです。
子どもの問題行動、不適応行動などの突発的な出来事によって目標が揺らぎ、その達成がなされないままに終わったり、目標が不明確になってしまったりすることすらあります。
しかし、目標から逆算して学級経営の計画を立案することは、実現したい学級の姿を描いてから必要なプロセスを決めていくので、目標を見失うことや目標から大きくずれてしまうことを最小限にとどめることができます。
今ある学級経営の最適解「自治的集団」と「創発学級」
ただ、学級経営におけるバックキャスト思考にも留意点があります。
教師の描く物語と一人ひとりの子どものそれは、皆それぞれ異なるということです。当然のことながら、教師の計画どおりに学級経営は展開されないわけです。教師と子どももそうですが、子ども同士もみんな異なる理想やニーズを持っています。

国立大学法人上越教育大学教職大学院教授
19年の小学校勤務を経て2008年4月より現職。現在は、教員養成にかかわりながら小中学校の教育活動改善支援、講演、執筆活動をしている。学校心理士、日本授業UD学会理事、日本学級経営学会共同代表理事、NPO法人全国初等教育研究会(JEES)理事。『指導力のある学級担任がやっているたったひとつのこと』『アドラー心理学で変わる学級経営』『学級経営大全』『明日も行きたい教室づくり クラス会議で育てる心理的安全性』(いずれも明治図書出版)、『赤坂版「クラス会議」完全マニュアル 人とつながって生きる子どもを育てる』(ほんの森出版)など著書多数
(写真:赤坂氏提供)