苦情対応歴30年のプロが語る「モンスターペアレント対応」こじらせないコツ トラブルが長引く原因は「教師や学校」にある
学校側はこうした状況の変化を重く受け止めず、「児童生徒を預かっているのは学校なのだから、保護者が自分たちの考え方に同意するのは当然」だという態度を続けてしまい、保護者の不信感を募らせ、問題を大きくしてきたところがあると思う。
働き方改革のためにも「苦情対応を学ぶ機会」が必要
筆者は苦情の対応に携わり、間もなく30年になる。対応時の緊張は薄れたが、その場で相手を推し量らねばならない難しさは変わらない。今は電話やネットでの対応が主流だが、対応が楽なのは対面である。しかし、教員は対面の仕事が多いにもかかわらず、主に児童生徒を相手にしていることもあり、保護者対応は苦手なようだ。
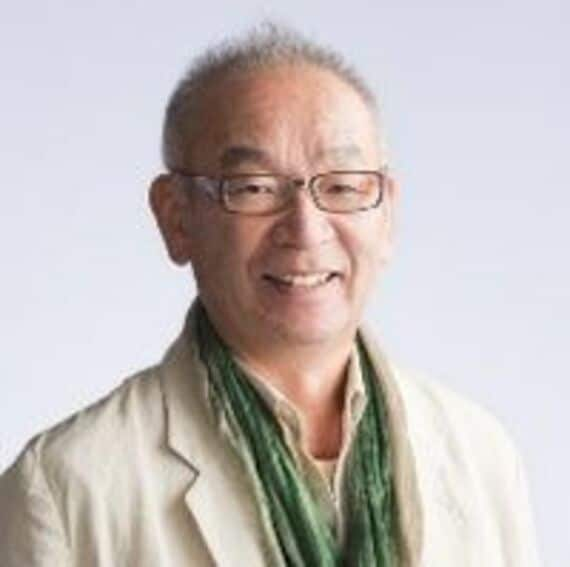
苦情・クレーム対応アドバイザー
大手百貨店のお客様相談室にて、数々のクレーム処理を担当した経験を生かし、苦情対応の第一線に立ち続ける。民間企業をはじめ、官公庁、学校、銀行、病院など、全国さまざまな業界での講演活動も行う。浅井企画所属。著書に『なぜあの教師は保護者を怒らせるのか――プロ直伝!学校の苦情取扱説明書』『なぜあの保護者は土下座させたいのか――謝罪事件から見えた新モンスターペアレント問題』(ともに教育開発研究所)、『教師はサービス業です』(中央公論新社)など
(写真:関根氏提供)
保護者の変化も対応を難しくさせているだろう。昨今の保護者は、自分たちの主張の根拠となる材料を準備し、子どもやママ友などと連携して味方をつけたうえで正論として申し入れてくる。学校側はその申し入れの内容を初めて聞くこともあり、その場で詳細までを理解することは難儀だ。
モンペは、対応に納得しなければ大声で怒鳴ることもある。人は罵声などで一度脅かされると再発を恐れ、それ以降は、怯み、対応に身が入らないものだ。この場合には平常心を保ち、冷静に怒声はやめてほしいと伝えるべきなのだが、そうした心構えや対応を教えてくれる人は、きっと職員室にはいないのだろう。
また最近では、イチャモンをつけて金子を狙う保護者も現れている。ちなみにこれは学校現場に限らずどの業界にも共通する傾向だ。
このような状況を踏まえれば、苦情対応の研修が必要であるはずだが、不思議なことに教師がモンペについて学ぶ機会があるといった話は今もあまり聞こえてこない。モンペ対応で本業の時間を削られている教師も多いことだろう。働き方改革について真剣に考えるのであれば、教育委員会も保護者対応について学ぶ機会を設定すべきではないだろうか。
新年度、押さえておきたい保護者対応のポイント
新年度を迎え、保護者との関係づくりも新たにスタートする時期なので、長年の苦情対応の経験を基に、保護者対応のポイントをお伝えしたい。






























