インクルーシブ教育の現状と課題。文科省の取り組みと日本国内外での事例を紹介

インクルーシブ教育とは?
インクルーシブ教育とは、「子どもたちの多様性を尊重し、障害のあるなしなどにかかわらず、すべての子どもを包含する教育方法」を指します。2006年の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示されました。
誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合える共生社会の形成を目的としています。
日本では、共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づく「インクルーシブ教育システム」の理念が重要であり、その構築のため、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意することが必要であると考えられています。
「特別支援と通常学級の子は違う」を取り払う、インクルーシブ教育の本質
文部科学省とインクルーシブ教育について
文部科学省では、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システムを構築するため、以下のような取り組みを行っています。
・乳幼児期を含め早期からの教育相談・支援
乳幼児期を含め、早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を目指します。必要に応じて、子ども・保護者と市町村教育委員会、学校などが、必要な支援について合意形成を図っていくことが重要であると考えられています。
・ 就学先を決める仕組み
「障害のある子どもは原則特別支援学校に就学する」といった仕組みを改め、障害や発達の程度、本人や保護者の意見、専門家の意見、学校・地域の状況を踏まえて総合的に判断できるよう、就学先決定の仕組みづくりに力を入れています。
また、就学後の児童生徒の発達の程度、適応の状況等を見ながら、柔軟な転学ができるよう体制の整備が行われています。
・一貫した支援の仕組み
障害のある子どもが、乳幼児期から成人するまで一貫した支援ができるよう、必要に応じて関係機関が連携できるような仕組みづくりも行っています。
・ 合理的配慮や基礎的な環境整備
障害のある子どもが、ほかの子どもと教育を受ける権利を守るため、学校が必要な変更・調整などを行う「合理的配慮」。一人ひとりの障害の状態やニーズに応じて配慮する内容を決定します。決定後も、発達の程度、適応の状況などを勘案しながら柔軟に見直し、合理的配慮を充実させるための基礎的環境整備も求められています。
ギフテッドではなく「特異な才能のある子」、個別最適な学びの中で支援へ
インクルーシブ教育と特別支援教育の違い
「特別支援教育」は、2007年から「学校教育法」に位置づけられました。「障害のある子どもの自立と社会参加をするための主体的な取り組みを支援する」という視点に立ち、「対象となる子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を確認して伸ばし、学習や生活で抱える困難さを軽減し改善するための適切な指導や支援を行う教育」を指します。
インクルーシブ教育は、前述したとおり、障害のある子もない子も共に教育を受けることで、「共生社会」の実現をめざす教育です。
共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために欠かせないのが、障害のある子どもが主体的に社会へ参加するための特別支援教育という位置づけになっています。

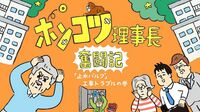





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら