高校国語「現代の国語」は教員泣かせ? 文章ジャンルで科目分けに賛否両論の訳 実践的なシチュエーションの再現難しく「困惑」
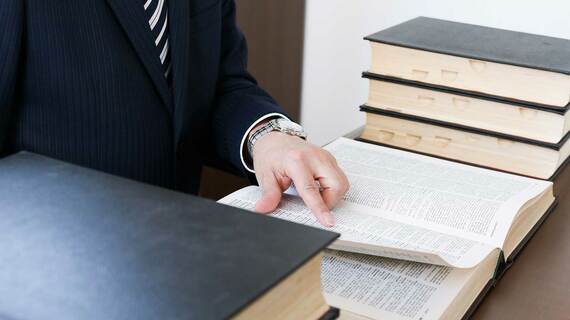
会社の新人研修が前倒しされて高校国語に
2022年度導入の新学習指導要領で、高校国語が再編された。中でも話題を呼んだのは、共通必履修科目の「国語総合」(4単位)が、「現代の国語」と「言語文化」(各2単位)に分かれた点だ。「現代の国語」は論理的・実用的な文章、「言語文化」は上代から現代までの文学作品などの文学的文章を扱うと捉えられており、さらに選択科目が「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探究」(各4単位)と定められた。

愛媛大学教育学部講師
大阪教育大学特任准教授、大阪大学大学院人文学研究科招へい研究員を経て、2023年4月より現職。 ひつじ書房ウェブマガジン「未草」にて「『現代の国語』と『言語文化』の問題点」を連載。 9月1日応募開始の中高生日本語研究コンテスト実行委員(主催・日本語学会)も務める
(写真:本人提供)
今回の高校国語再編の意図を、愛媛大学教育学部講師の清田朗裕氏はこう解説する。
「かつて若者が『金の卵』と言われた時代は、いち早く社会に出て労働力となることが望まれました。しかし、現代の子どもたちが生きるのは、文部科学省や中央教育審議会が定めるところの『知識基盤社会』です。さらに今後は、世界をも相手にしなければならず、OECDが行うPISAの結果なども踏まえて世界の同年代の子どもたちが持つ力を意識した教育も必要になりました。今回の再編は、日本の子どもたちが知識基盤社会を豊かに生きるための資質・能力の育成を目的としています」
新学習指導要領は、高校国語で目指す資質・能力として、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等、という3つの柱を掲げている。
「従来の高校の授業は、教員が一方的に『AとはBだ』と結論を教え、その板書を生徒が書き写すスタイルが主でした。それが新学習指導要領では、『言語活動』を重視した授業へと変わっています。例えば、教員が『Aとは何か?』と投げかけ、生徒がそれを自ら考え議論するプロセスが重視されるのです。ただし、こうした授業を十分に行うには、実際はもっと時間が必要です」
「知識基盤社会」ではとくに「聞く力」「話す力」が必要になると清田氏は語る。実際、生徒の多くが卒業後すぐに就職する高校では、「国語表現」という授業でプレゼンテーションやディスカッションに向けた指導が行われてきた。今後はこうした動きが全国的に広がることになるが、これらは今まで、主に会社の新人研修でも扱われてきた内容だ。






























