さらに、家庭科の調理実習が中止になったり、公立学校でも掃除を清掃業者に委託するなど、最低限の生活力を身に付ける機会さえ失われたと柴崎さんは嘆く。学校は、静かに勉強する場所になってしまった。
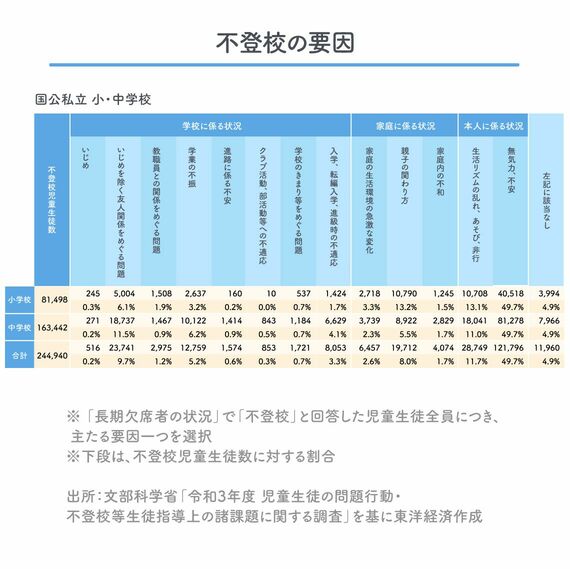
教育予算が少ない日本、クレームの多い社会での子育て
不登校の中でもとくに中学生は、高校生のように大学入学資格検定やアルバイトにも挑戦できず、いま自分が何をすべきなのかを見失いがち。その不安からくる憂鬱も相まって長期間休み続けてしまう印象があるという。登校しても、授業がわからず定期テストも解けないのが明白とあって、どんどん復帰しづらくなる。最近の大人は「無理して学校に行かなくてもいいよ」とやさしく声をかけるが、ではどうすればよいかまでは教えてあげられないのだ。
柴崎さんは、「個別の補講など、勉強の遅れを取り戻すためのワンクッションが必要」だと話す。経済的に余裕があれば個別指導塾や家庭教師を活用できるが、コロナ禍で経済状況が変化した家庭も多く、公的支援がいると主張する。
「学校でなくても構わないので、勉強を続ける場所は確保すべきです。フリースクールなどは月謝が数万円かかりますが、資金さえあれば、地域の公民館や図書館でもこうした場が提供できるはず。一時期、フリースクールを公的な教育機関と連携させる議論もあったようですが、コロナ禍でいつの間にか立ち消えてしまいました。とはいえ、東京五輪には膨大なお金が使われましたし、今後は防衛費も増額しますよね。国の将来を考えるなら、もっと教育に予算をつけてほしいと切実に思います」
しかし仮に資金の問題をクリアしても、公共施設に子どもを集めると防犯や騒音の観点から非難されたり、教員免許のない人が指導に当たることに反発がくるなど、まだまだ障壁はあると柴崎さんは指摘する。放課後の学童保育のスタッフが善意で勉強を教えることにもクレームが入るこの社会は、子どもを真の意味で幸せにすることができるのだろうか。
不完全な「インクルーシブ教育」で進む不平等
発達障害の生徒への対応にも疑問があるという。例えば聴覚に障害がある生徒の場合、教室内のすべての音が同じ音量で聞こえてしまうことがある、先生の声を拾うのが難しい。確実に、静かな環境で個別に学ぶ必要があるにもかかわらず、柴崎さんが勤めてきた学校の1つでは「インクルーシブ教育」という名の下に、障害がある生徒もできる限り同じ教室で学ぶよう指導されることもあった。その背景には経費削減の意図があるのではないかと柴崎さんは言う。実際、特別支援学校は養護教諭の人件費も高く、普通学校より約7倍のコストがかかる。その中で発達障害とされる子どもが急増したため、こうした対応が取られたとも考えられる。

しかし、読み書きがスムーズにできない生徒にとっては「教室にいるだけ」の時間となり、教育の機会としてはむしろ不公平だと柴崎さんは感じている。
「発達障害の1つである学習障害では、例えば先生が黒板に書いた『あ』の文字が、教科書の『あ』とほんの少し違うだけで認識できなくなってしまうこともあります。デジタル活用なら対応できるのですが、中学校の定期テストは手書き解答と決まっているので、彼らは点を取ることができません。






























