デジタル・シティズンシップ教育とは?注目されている背景や海外・日本での取り組みについて解説
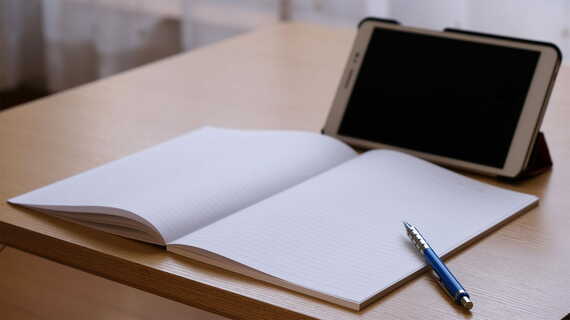
デジタル・シティズンシップとは?
デジタル・シティズンシップという考え方は、International Society for Technology in Education (ISTE)が広めたとされています。
具体的にはISTEが作っているNational Education Technology Standard for students(NETS)の2007年改訂版の中でデジタル・シティズンシップについて言及され、、2015年には次のような定義を示しています。
「生徒は相互につながったデジタル世界における『生活・学習・仕事』の『権利・責任・機会』を理解し、安全で合法的かつ倫理的な方法で行動し、模範となる」というものです。
デジタル技術の利用を通じ、責任ある市民として社会に積極的に参加するための知識や能力といえます。
引用: International Society for Technology in Education (ISTE)「ISTE STANDARDS: STUDENTS」
また、上記記事では、以下のように説明されています。
「簡単に言うと、ICTのよき使い手になると同時に、よき社会の担い手になることを目指す教育です。今、インターネットが社会インフラとなり、若い人たちは普通にSNSを使っています。その現実を前提に、市民としてどう生きていくべきかを考えさせ、責任あるICTの使い方と社会への貢献の仕方をしっかり教えようというもの。つまり、ネット空間だけのシティズンシップではなく、『デジタル時代のシティズンシップ』を育てていく教育なのです。」
引用:デジタル・シティズンシップ教育広がる納得理由 | 東洋経済education×ICT | 変わる学びの、新しいチカラに。
つまり、ICT機器の活用を大前提とするGIGAスクール構想の実現に向けた、本質的な教育活動と言えるのです。
デジタル・シティズンシップの背景
現代の私たちの生活において、情報端末や高速大容量の通信ネットワークはもはや必需品です。現代の子どもたちの世代は、生まれたときからデジタル環境に触れている「デジタル・ネイティブ世代」ともいえます。

しかし、「デジタル・ネイティブ」であったとしても、新しいテクノロジーが生活にどのような影響をもたらすかなど、学校組織における児童・生徒としてだけではなく、社会を構成する一員として子どもたちが理解しているとは限りません。
Society 5.0は仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を指します。この時代で生きていく子どもたちにとって必須となる、デジタル・シティズンシップ能力は、自然と身に付くものではなく、学んで実践する必要があるのです。































