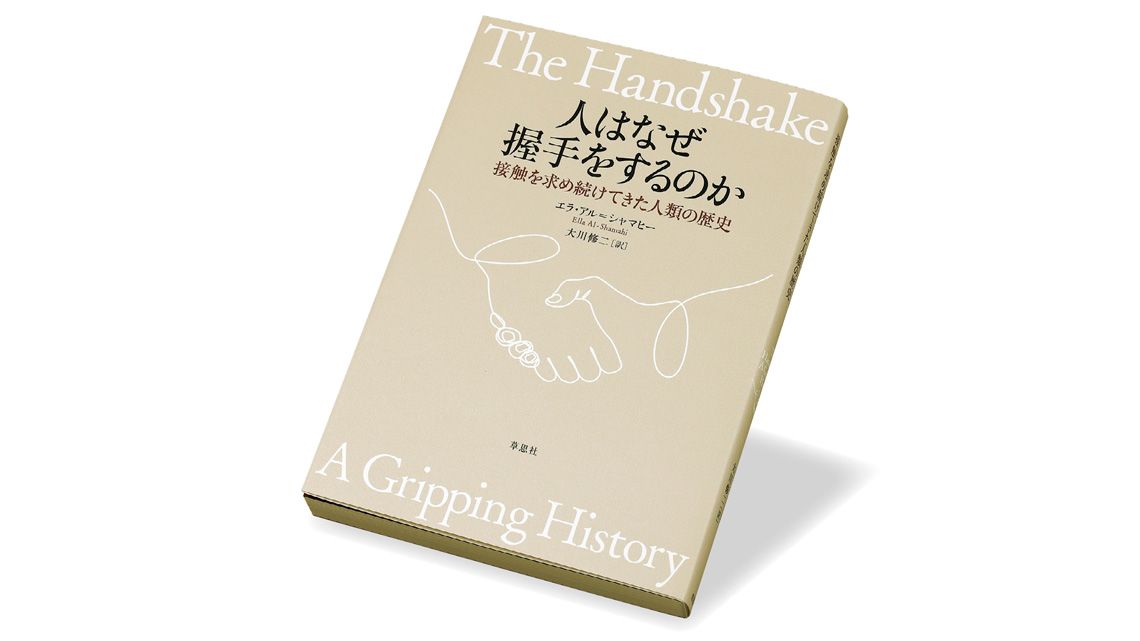
[著者プロフィル]Ella Al-Shamahi/『ナショナルジオグラフィック』の探検家にして古人類学者、進化生物学者。スタンダップコメディエンヌでもある。専門は洞窟、非友好的地域、紛争地域、不安定地域などの探検とネアンデルタール人。遺伝学、分類学、生物多様性の学位を持つ。
コロナ禍が始まってしばらくして、政治家たちは握手を避け、「ひじタッチ」や「爪先タッチ」をするようになった。そのころ評者は、近代以降、政治にとって三密(密集・密接・密閉)は不可欠であり、いずれ握手も戻ってくるという小文を書いたことがある。実際、その後の選挙では岸田文雄首相が有権者と拳を合わせる「フィストバンプ」を多用し、今となっては握手がすっかり復活している。コロナ禍の中で著された本書も握手は必ず戻ってくると論じる。ただし、議論ははるかに壮大だ。
握手という文化
日本における握手は幕末・維新後に普及したというのが一般的な理解だろう。日本からは握手は西洋的な文化に見える。ところが、探検家でありコメディエンヌでもあるこの若手人類学者は、未接触部族にも握手の慣習があることを指摘してこうした見方を一蹴する。握手は人類に、いやもしかしたら人類誕生以前から不可欠なものとして埋め込まれている、万国共通のものだと主張するのだ。

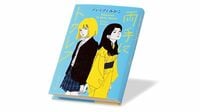

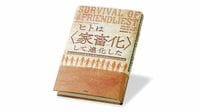




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら