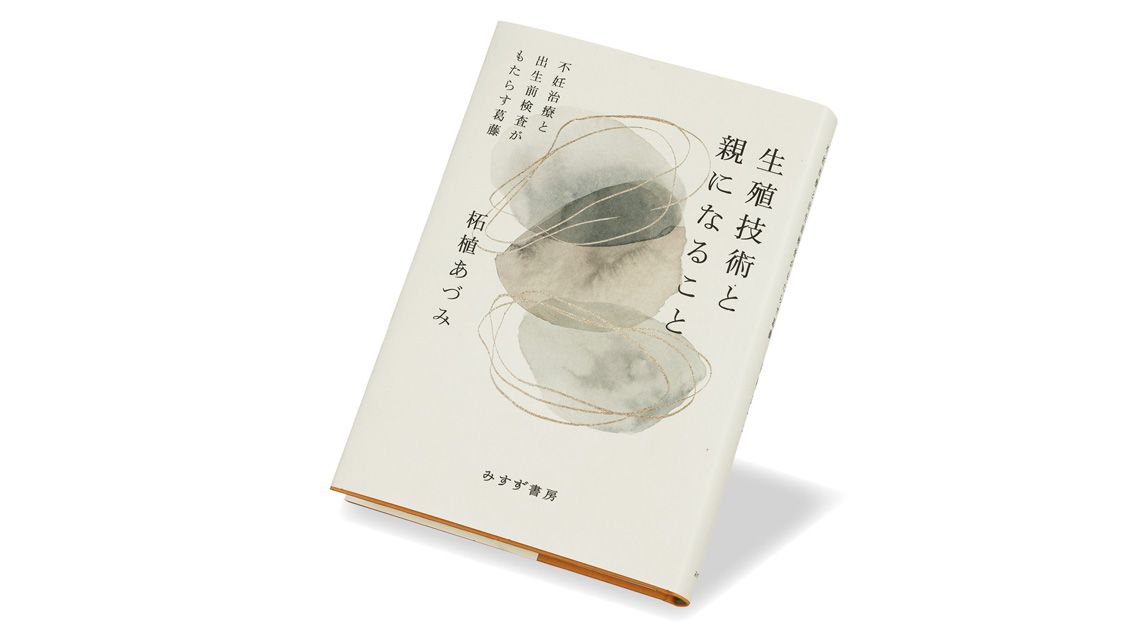
[著者プロフィル]つげ・あづみ 1960年生まれ。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程満期退学。同大学から博士(学術)授与。明治学院大学社会学部教授。専攻は医療人類学、生命倫理学。著書に『文化としての生殖技術』、『妊娠を考える』など。
非配偶者間人工授精について知ったのは、医学生だった三十数年前だ。
第三者から精子の提供を受けての妊娠は、「夫婦間に子どもが生まれる」と言えるのだろうかと疑問が湧いた。また、異父兄弟姉妹が出会って婚姻関係を結ぶこともあり得、ちょっと危険なのではないかと感じた。さらに、自分が非配偶者間人工授精で生まれたと知ったら、自分の生命は人工的に作られたと思わないだろうかと、「生まれさせられる側」の心理まで考えたりした。
このシステムは世間で大きな議論にならずに受け入れられているように見えた。インターネットのない時代で、関連する書籍も見つけられなかった。自分の感覚は世間からずれているのかと考え込んだりもした。しかし、違和感が残ったことは間違いなく、生殖補助技術は不自然だという思いのまま今に至っている。

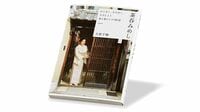
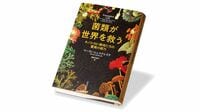





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら