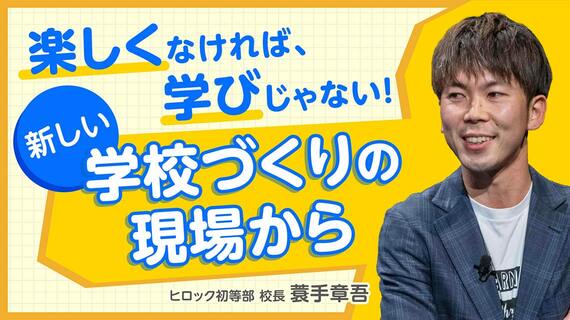当初は途方に暮れていた自分でしたが、学ぶにつれて試してみたいことが増えていきました。試すことで子どもたちの姿や関係性、成長に変化が見られ、改めて学ぶことの楽しさを実感できました。
そんなやりがいとともに、これまで自分が通常級で行ってきた実践に多くの疑問が湧いてきました。自分が当たり前のように努力を強いてきたことは、本当に正しいことだったのだろうか?子どものために行ってきた支援は、本当に子どものためになっていたのだろうか?と。
とくに考えさせられたのが、インクルーシブ教育です。現在、すべての通常級で特別な支援が講じられていると思います。私も特別支援学校に行く前までは「正義」として特別な支援をしてきましたが、そもそもマジョリティーや大人の理想を「普通」という言葉で囲い込み、マイノリティーに「特別」とレッテルを貼って目立たないようにしていること自体に違和感を感じるようになりました。
もともと人はみんな特別であるべきだろうし、普通やマジョリティーなんてそもそも幻想なのではないか。真にインクルーシブ教育を実現するには、通常級の改革が必須という結論に至った私は、3校目の異動で再度通常級に戻り、その後も試行錯誤しながら実践を重ねてきました。
一方で、特別支援教育に対して感じる違和感は、ペースを落として通常級の学びを追いかけさせようとしているものが多くあること。人より後れていると認識させられながら2倍、3倍の努力で追いつけるように強いられるのは誰だってつらいはずです。優劣やスピードではなく、すべての人が学びを楽しめる環境をつくれないのかというのが、目下自分の関心事であり、人生を懸けて探究していきたいテーマです。
もし4月から初めて特別支援を担当される方がいたら、ぜひ1人ひとりの特性や違いを、劣っているとか後れているという見方ではなく、自分が知らなかった1つのあり方としてフラットに受け取ってみてください。きっとその出会いが、自分の人生をより豊かにしてくれると思いますよ。
(注記のない写真:つむぎ / PIXTA)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら