20万円から3500円に活動費減!「PTA広報誌」廃止のメリットがすごい 組織刷新、ICT化を進める鴻巣中央小学校の場合
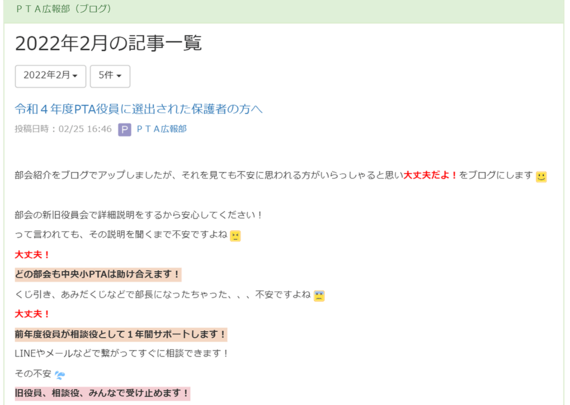
(画像出所:鴻巣市立鴻巣中央小学校ホームページ)
「お手紙だと印刷や配付が伴うので、保護者に届くまで1週間以上かかったと思います」と、小林氏。石井氏も、「お手紙であらたまって『大丈夫です』と通知されると逆に不安になってしまいそうですが、ブログはいい意味でライトに伝えられますよね」と話す。
楽しさのカギは、各部が独立した「失敗OK」の組織
「保護者目線の記事は、学校の発信とは違ったよさがあり、多くの人に学校を知ってもらう一助になっています。広報部の皆様は超積極的で、どんどん投稿が増えていますね」と、清水氏は笑う。
しかし、投稿数にノルマがあるわけではない。学校に行ける人が行けるときに取材し、投稿作業もそのときにできる人がやってきた。
「仕事を持つ部員も多いので『できることをやればいい』を前提にしているのですが、それでも投稿が多いのは、みんな楽しいと思っているから。ブログは初めての試みだったので、試行錯誤の中で絆が深まっていった面もありますね」(小林氏)
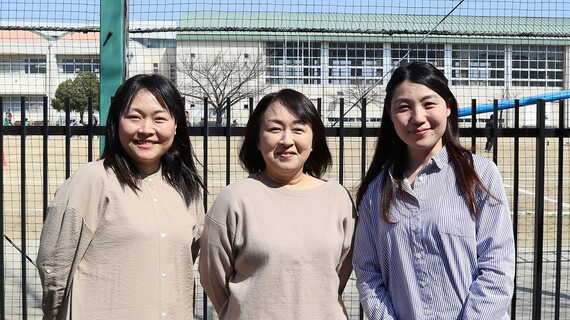
(写真:鴻巣市立鴻巣中央小学校提供)
部員同士はLINEグループで連絡を取り合っており、わからないことを投げかけると誰かが必ず解決してくれる。そんな協力的なメンバーに恵まれたことも大きいが、主体的なチームワークを築けるのは、そもそもPTAの組織体制にあるという。
実は、同校のPTAは、2016年に前校長と当時のPTA会長の改革により、運営部・広報部・環境部・バザー部・資源回収部・安全部・地区部の7部会体制とする「PTA会長と執行部を置かない組織」に刷新された。各部10人程度の役員で構成して部長は置くが、各部が独立して仕事を完結する横並びの組織に変わったのだ。
小林氏は、過去に旧体制のPTAも経験している。当時は、各部が執行部の下部組織であったため、受け身の活動になりがちで「失敗できない」という緊張感があった。しかし現在は、活動内容は各部が自由に決定でき、「失敗OK」のポジティブな雰囲気に変わったと感じている。
「運営部長が『失敗しても、検証して来年うまく運営できればそれでいい』と言ってくれるので、以前と比べてすごく保護者の気が楽になったと思います。ほかの専門部長からも、自ら引き受けた役員ではなかったけど、楽しい経験ができたという声がたくさん聞かれます」(小林氏)
同校では、子ども1人につき1回は役員をやる前提で、立候補とくじ引きで部が決まるため、本意ではない活動に当たることもある。しかし、それでも保護者が前向きになれるのは、裁量権が大きなカギとなっているようだ。そして「一人の百歩より、百人の一歩」を大切にした運営を目指す清水氏のリーダーシップにより、この体制のよさが生かされていると感じる。
学校と保護者がやり取りする「ネット基盤の構築」は難しい
清水氏は、「運用ルールを慎重に整備する必要はありますが、USBで保存しているPTAの引き継ぎデータを、edumapのファイル保存機能を活用した形でのクラウド保存も検討しています」と話す。広報部は写真管理を「各自のスマホなどで行っている」(石井氏)そうで、クラウドで所定の保存場所ができればさらに業務はスムーズになるだろう。






























