コロナ禍のPTA「オンライン化」で前例踏襲に変化 これまでの活動を見直してスリム化、効率化へ
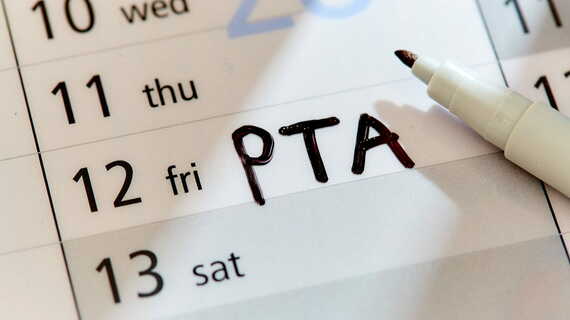
PTA総会、新1年生交流会などコロナを機に活動をオンライン化
「PTA活動のオンライン化を進めたことで、これまでの活動の“棚卸し”ができていることを実感しています」と語るのは、神奈川県川崎市内の公立小学校PTA(児童数960、世帯数830)で2020年度から会長を務める保﨑幸一氏。きっかけは、20年3月から6月のコロナ休校だった。

川崎市内の公立小学校PTA会長。役員経歴は、2018年〜19年副会長、20年より現職。2児の父
(画像は本人提供)
「毎年5月に対面で行っていたPTA定期総会の開催が不可能になり、さあどうしようかと。活動計画や予算の議案が通らないと、その年度のPTA活動ができないため、急きょ、オンラインを活用した『書面総会のWeb開催』に踏み切りました」
保護者への連絡ツールとして、すでに導入していたメール配信システムを活用し、総会資料はPTA会員のみが閲覧できる形でPTAの専用ホームページ上に掲載。会員は、各家庭のパソコンやスマートフォンから内容を確認できるような仕組みを整えた。議決および委任はGoogleフォームで行い、自動集計で回答を確認した。
「初めての試みでしたが、8割近くの保護者が議決権を行使し総会が成立。議案も承認されました。対面総会の際に行っていた、PTA役員による会場設営や当日の議事進行、総会資料の印刷や配布、投票用紙の回収、集計などの手間が大幅に省けただけでなく、『Web移行で参加しやすくなった』という声もいただきました」(保﨑氏)
20年のゴールデンウィークには、休校期間中の不安解消を目的に、PTA主催で「20年度新1年生Zoom交流会」を実施した。発案したのは、20年度副会長の増島佐和子氏だ。
「当時はZoomを使い慣れない保護者もいたため、PTAのホームページにZoomアクセスマニュアルを掲載したのに加え、当日を迎える前にアクセス確認日を設け、役員が事前フォローを行いました。交流会は、多くの参加者が見込まれる日曜日に開催。校長先生にも参加いただき、初開催だったにもかかわらず約6割の家庭が参加し、終了後のアンケートでは、参加者の9割から『とてもよかった』という声が寄せられました」
PTA主導のこれらの取り組みに学校側も並走するように、学校全体で、全学年クラスごとのオンライン朝の会を試行したり、YouTube限定配信による学校説明会などが導入されたという。
オンライン化が、PTA活動の見直しや改善につながった
PTA主催の保護者向け講演会も、Zoom開催を実現。さらに“子どもたちのお祭り”的な意味合いが強かった「PTA文化祭」も、「子どもたちの未来につながる学びのプログラムを」という学校からの要望を組み込み、「世界幸福度ランキング上位の国、フィジーの人とオンラインでつながろう!」「オリンピックで使われるスポーツピクトグラムを学ぼう」などを企画し、オンラインで開催した。
PTA活動を「コロナ禍だからできない、やらない」で済ませてしまうのではなく、「この状況の中で何ができるか」と発想を転換し、同校ではポジティブな姿勢でPTAのオンライン化を進めてきた。



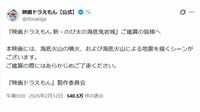




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら