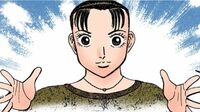「学力世界一」シンガポールの教育は何が凄いか TIMSS「勉強は楽しい」割合に日本の課題あり
「日本でも、今回の学習指導要領から『主体的・対話的で深い学び』に力点が置かれていますが、シンガポールでは17年からいち早く小学校1・2年生で必修教科として『アクティブ・ラーニング・プログラム(PAL)』を導入しました。学級担任が担当するPALでは、身体表現、アウトドア、スポーツ・ゲーム、美術制作の4領域での体験活動を通して学習意欲や協調性、創造性や探究力などを高め、教員との交流も深めながら、総合的な人間力の育成や学習活動全般の質の向上を図っています。
ICTを用いた教育環境も充実していて、シンガポールではコロナ禍においても、小学校から高校まで休業は1日もありませんでした。このような事態に備えて、以前から年に2回、在宅オンライン学習の日を設けて、子どもたちは教育省が準備した学習プラットフォームでオンライン学習の訓練を受けていました。昨年4月、ロックダウン措置が取られた際には学校が閉鎖されたものの大きな混乱はなく、小学生も保護者の支援を得ながら1カ月間在宅でオンライン授業を受けました」
もう1つ、シンガポールの教育における大きな特徴が習熟度別、能力別の学習システムだ。小学校高学年(5・6年)になると各教科で習熟度別クラスに分かれるのに加え、卒業時には国家試験として小学校卒業試験を受ける。その後、中学校では能力別クラスに分かれて異なるカリキュラム、教科書で学ぶのだ。
こうした制度には賛否両論があるようだが、一人ひとりの能力に合わせて学ぶことができることから、学習課題が適切となり、学びへの意欲が減退することなく学習に取り組むことができるという点では注目できる(24年度までに中学校でも教科ごとの習熟度別編成に移行する予定)。一方で、TIMSS2019では「算数の学習に自信がある」「理科の学習に自信がある」の回答は国際平均よりも低かったなど、成績と自信が結び付いていない点ではシンガポールにも課題はある。
今後日本では、学習意欲を高めるのに重要な「勉強は楽しい」と感じる授業をどう展開していくべきか。20年以降、日本でもさまざまな教育改革が進んでいるが、STEAM教育の視点やシンガポールをはじめとする各国の取り組みは大いに参考になりそうだ。
(注記のない写真はi-Stock)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら