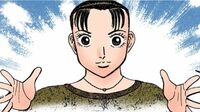「学力世界一」シンガポールの教育は何が凄いか TIMSS「勉強は楽しい」割合に日本の課題あり
だが、現実の世界と文脈づけて学ぶには、教科ごとに教えていては限界がありそうだ。STEAM教育を研究する山内氏は、教科横断的に学びを進める利点についてこう説く。
「もともとSTEAM(Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics)は、STEMから始まっていますが、数学や理科の応用としてテクノロジーやエンジニアリングが位置づけられています。理科や数学が自分の将来とどう関わるのかについて考えるうえで重要なのが技術や工学であり、ここにイノベーションを創出するために重要な概念として、芸術あるいは教養であるアートが入ったわけです。
とくに現代的な課題は、はっきりと答えがわからないものが多い。はっきりと正答が出せる数学や理科と違うタイプの授業を行う必要があると考えています。STEAMのような教科横断的な学びは、物事を重層的かつ多面的に見る力がつく。そうした授業を教員一人だけで行うのは難しいにしても、学校全体で取り組んだり、外部の専門家と協力するなど、現実世界と文脈づける実践を重ねていけば、算数・数学や理科が自分の役に立つことやその楽しさが伝わると考えています」
シンガポールがトップを独占する理由
TIMSS2019の成績を世界各国で比較してみると、シンガポールが小学校中学校の算数・数学、理科ともにトップを独占していることに気づく。シンガポールはPISA2018においても、全参加国中すべてで2位という結果を残している。


シンガポールの教育事情に詳しい山梨県立大学 教授の池田充裕氏は、「シンガポールは数学、理科ともに高度な学力を持つ層が他国に比しても厚くなっている。一方、低学力層においても、学力の改善傾向が顕著であり底上げにも成功している」と説く。
確かに得点別の割合を見てみると、例えば中学校の数学では625点以上の高得点層が日本は37%であるのに対してシンガポールは51%。理科では日本が22%で、シンガポールは48%と日本を大きく引き離している。参加国全体でも、シンガポールは数学・算数と理科の両方で、小学校、中学校ともに625点以上の高得点層、それに続く550点以上の割合の合計が最も高かった。また中学校の数学で高得点層が半数を超えたのはシンガポールのみだった。

筑波大学第二学群人間学類(教育学専攻)卒業。筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取得満期退学(修士〈教育学〉)。専門は比較教育学、国際教育学
(写真提供:池田氏)
「とくに算数・数学では推論スキル、理科では探究スキルに関わる設問で得点が高いことから、児童生徒が算数・数学や理科の課題に対して興味や見通しを持って学び、学習意欲を高めるような授業方法が浸透していることがうかがえます。実際『算数が好き』『理科が好き』といった学習意欲の面でも国際平均を上回っています」(池田氏)
シンガポールでは小学校教員であっても、養成段階から担当する専門教科が3教科に限定されている。しかも、現場教員には毎週、教材研究やチームでの授業改善活動の時間が与えられており、充実した教材作りと魅力的な授業をつくるための基盤になっているという。
日本の小学校でも、2022年度に教科担任制の導入が予定されているが、ただでさえ日本の教員は諸外国と比較して労働時間が長く、それが教材や授業の質、また学力向上にどう直結してくるかは現状では不透明だ。またアクティブラーニングやICT教育への取り組みという点で見ても、シンガポールは日本より対応が早い。