筆者は、民主党政権期の改革論議にも今回の改革論議にも有識者として関わったが、官僚が改革に抵抗したというより、衆参ねじれ状態で法案が成立しなかったのが実情である。もちろん、当該部局が独法の統廃合に、当初は反対したりすることはある。
研究開発系の独法を中心に、たまっていた不満
しかし、行政改革部局や独法制度を所管する総務省(総じて制度官庁を称する)が真っ向から立ち向かい、当該部局を説得して統廃合を含む独法改革の成案を得る努力をした。改革の成案についていったん閣議決定されれば、各省庁も抵抗しない。
独法制度は、独法通則法に基づいている。国の外郭団体はかつて特殊法人として、各省庁が独自に設立して、独自の都合よいルールで運営されていた。これを改め、独法通則法で共通ルールを定めて、経理や給与も特別扱いを認めない仕組みで、独法制度が運営されることとなった。
ただ、制度発足後、色々な種類の法人が独法になったため、独法通則法で画一的に運用していては、うまく任にあたれないとの不満も高まった。特に、本稿のテーマと関わることだけ取り上げれば、独法職員の給与は優れた研究者を含め国家公務員に準拠した水準にすることと、他の独法と同様に給与総額の一律カットを行わなければならないことと、長くても5年間の中期計画に拘束され、それをまたいで予算を繰り越したり流用したりできないことが、不満だったようである。
研究開発系の独法は、国際的に見て優秀な研究者は、各省事務次官より高い給与を出せるようにしないとスカウトできないとか、5年を超える研究を続けるための予算確保が事前に予見できないとかという支障がある、と問題視していた。
民主党政権期にも、国の研究開発振興に熱心な国会議員を頼りに、この不満を起爆剤に行動を起こす向きがあったが、行政刷新会議の事業仕分け(そういえば、理研の次世代スーパーコンピュータ事業もその対象だった)もあって、独法改革の議論の中で表立って反映されることはなかった。


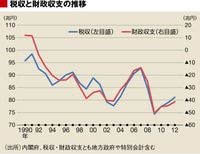




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら