37歳の脱サラで「だるま造り」始めた男の仕事観 ブライダル業界経て40前にやり直しを期した
ブライダル会社は新郎、新婦側と綿密に打ち合わせて、計画どおり和やかに結婚式を終えなければならない。レストランでの経験など問題にならないほど、接客の度合いが高いが、小野里さんには苦にならなかった。1人で黙々とこなす仕事も好きだが、会話を交わしてサービスを提供し、お客に満足してもらう仕事も好きだったのだ。
2年ほどして、会社は隣接する栃木県の宇都宮市に南仏風のハウスウエディング場をオープンした。小野里さんは宇都宮に派遣され、2人体制の責任者の1人に登用された。
式場は独立したハウスが8つもある大規模なもので、従業員はアルバイトを含め100人前後。1日に午前と午後、2回転することも可能だったから、最大16組が挙式できた。お客である新郎新婦にとっては人生最大といっていい晴れ舞台である。絶対、失敗は許されない。小野里さんの気苦労たるや大変なもので、完全徹夜することも珍しくなかった。
だが、会社が重視するのはあくまでも数字だった。小野里さんは営業方針に疑問を感じながら、現場の力でカバーしてきたが、それにも限界があった。
新聞記事をきっかけにだるまの道へ
37歳のとき、後任の責任者が決まった段階で会社に辞表を出した。8年間勤め、すでに結婚していたが、奥さんも退職に目立った反対は唱えなかった。40前ならまだやり直しが利くと考えていた。
退職後、何をするかアテはなかった。ある日、実家に行くと、母親が新聞を片手に「ねえ、これどうかしら」と記事を見せた。高崎だるまの製造協同組合が後継者を募集しているという記事だった。
「いいかもしれない」と小野里さんは直感し、応募した。組合主催の説明会には約50人が集まった。秋田や福岡からも志望者が来た。激戦だったが、小野里さんは組合が選んだ3人のうちの1人に選ばれた。
太田市から高崎市の親方の工房まで毎日1時間半かけて通勤した。親方は一人前になるのに10年かかると言ったが、妻と子ども2人がいる。悠長なことは言っていられない。一生懸命通って製造の基礎を身に付け、8年で独立を許された。
だるまの張りぼては別に専門業者がいる。それを仕入れて、手作業で色入れし、売り物になるだるまに仕上げ、お客に売る。手工業そのものだが、それでも仕事の進路や方針を自分で決められる。小野里さんはもちろん、だるまに転じてよかったと感じている。
(『ウェッジ』2018年2月号)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

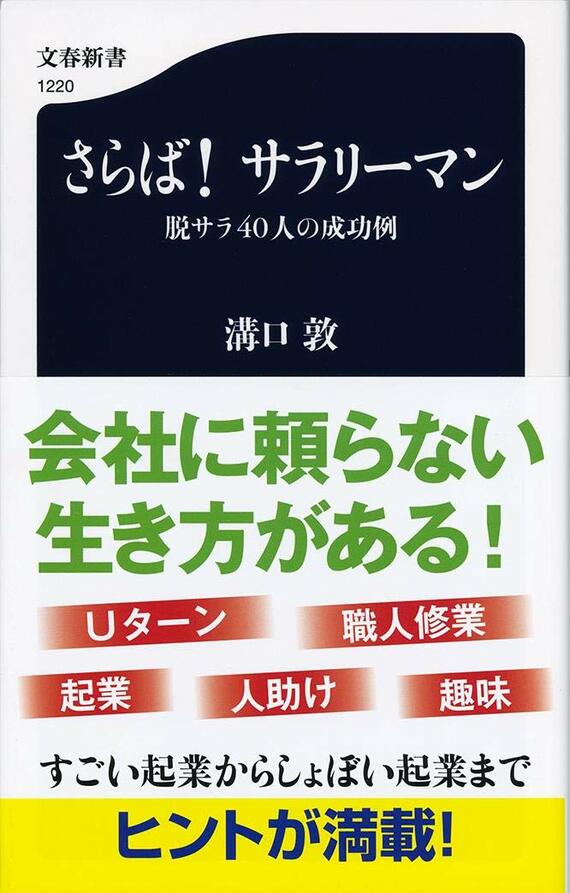






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら