映画製作者が語る、香港の未来に募る危機感 中国本土で上映禁止になった香港映画「十年」

香港の街中で紅衛兵をイメージさせる制服を着た少年団と遭遇した。彼らは「よくない言葉」が書き込まれた紙を持ち歩きながら、商店や書店を見回っている。まるで文化大革命の時代にタイムスリップしたかのようだ。
これは香港の5人の監督によるオムニバス映画『十年』の中の第5話、「地元産の卵」の1シーンだ。だが、実際に映画が公開された直後、中国当局によって、銅鑼湾書店の関係者が連れ去られる事件が発生。本作は事件を予知していたのではないかと大きな話題を呼んだ。
2015年12月に香港の単館で上映された『十年』は、書店の事件もあり、同館の週間興行成績で、同時期に公開された『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』をしのぐヒットとなった。
その後、中国政府によって中国本土の映画館での上映は禁じられるなど、中国内で大きな物議を醸した。一方で香港各地の大学で上映と討論会の開催が活発化し、2016年4月には香港のアカデミー賞と言われている「香港電影金像奨」で最優秀作品賞を受賞した。
7月22日から日本で上映が始まった。今回は映画のプロデューサーであり、「地元産の卵」で監督を務めた伍嘉良(ン・ガーリョン)氏と、エグゼクティブ・プロデューサーの蔡廉明(アンドリュー・チョイ)氏に話を聞いた。
映画製作中に雨傘運動が勃発
――『十年』を企画した経緯を改めて聞かせてほしい。

伍:ドキュメンタリー映画を撮っている時に、香港は将来変わることができるのかということを考えるようになった。いろいろな人に「10年前の自分が今の自分にどう影響しているか。今どのような困難に直面しているのか。そして将来自分はどうなるのか」を取材した。みんな10年後の自分や香港のことをさまざまな角度から想像して話をしてくれた。これを映画にまとめたら面白いのではないかと思った。
――脚本執筆中の2014年には、学生たちが民主化を求めて雨傘運動で香港政府に抗議活動を行った。
伍:雨傘運動が起きたときに、現実は想像以上にふざけていると思った。映画の中で描こうと思ったことがすべて現実で起きてしまっている。
蔡:雨傘運動は失敗に終わり、正直落胆した。普通に選挙する権利など、基本的なものがなぜわれわれにはないのかと、悲観的な気持ちになった。同じように感じた人も多いだろう。この映画を見て、そういう人の傷が少しでも癒えればと願っている。

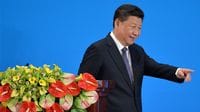































無料会員登録はこちら
ログインはこちら