子どもの運動、科学的に「実はNGなこと」とは? 成長期の発達を妨げる「3つのタブー」 《体育で定番の"持久走"も要注意…》
授業や練習の冒頭に、「動きづくり」の5分間を設けると効果的だ。
例えば、ミニハードルを使ったステップ練習、方向転換を含むフットワーク、体幹を意識した静的バランス運動などを行うと、動作の精度が高まる。映像を用いて自分のフォームを確認させることも、意識の変化に役立つ。
成長を支える運動環境とは
科学的に見ると、成長期に最も大切なのは「量」や「根性」ではない。神経・筋・骨の発達段階に応じて、適切な刺激と休息のバランスをとることが、健全な成長の条件である。
そのためには、
・単調な運動を避けること
・強度と休養のリズムを設けること
・正しい動作を早期に定着させること
この3つの原則を守ることが重要である。
子どものスポーツは「上達のための練習」ではなく、「発達を支える経験」として捉える必要がある。科学的な視点を導入し、発達に適した運動環境を整えることが、将来の競技力と生涯の健康を守る最も確かな方法だ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

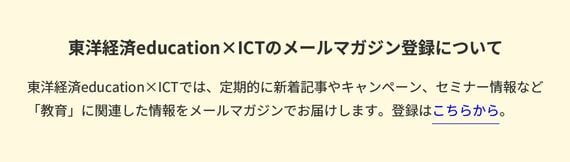































無料会員登録はこちら
ログインはこちら