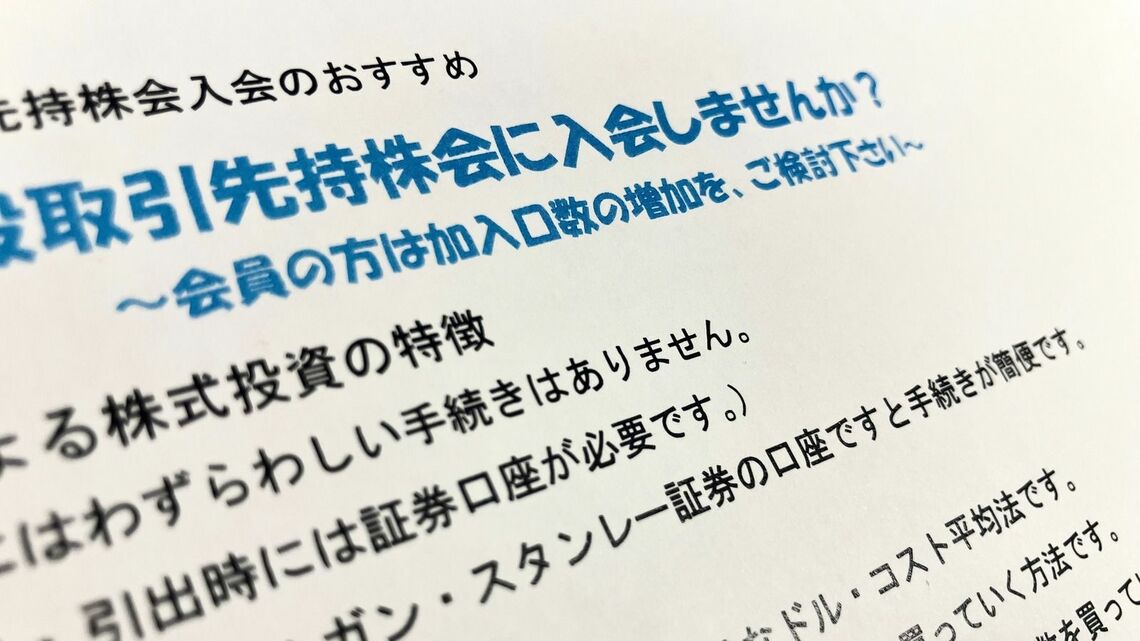
「取引先持株会に入会しませんか?会員の方は加入口数の増加をご検討下さい」
ある上場ゼネコンは、こんな文言から始まるチラシを作成している。曰く、口数に応じて毎月1万円から50万円を拠出すると、持株会がゼネコンの株を買い付ける。株価にかかわらず毎月末に一定額を投資し、配当金は自動で再投資される。チラシは「(持株会は)長期投資に最適」と強調している。
同じく取引先持株会を主催する複合機メーカーは、会員企業向けのウェブサイトを運営している。「取引関係にある企業等との緊密化を図る一助として、株式を取得しやすくするようお手伝いする」のが持株会の趣旨だという。前述のゼネコン同様、やはり会員は毎月一定額を持株会に拠出し、持株会名義でそのメーカーの株を取得する。
実態は「政策株積み立て」
取引先持株会はその名の通り、企業が資金を出し合って取引先の株式を共同で取得する制度だ。普及したのは1980年代から90年代。当時発行した転換社債やワラント債が株式に転換されて発行済み株式数が急増したことや、バブル崩壊で財務を痛めた金融機関が政策保有株式を手放したことを受け、安定株主を作りたい企業が相次いで設立した。今年5月にも、東証スタンダード市場に上場するパルマが、取引先持株会の設立を発表している。
互助会の様相を呈する取引先持株会だが、実態は「政策株の積み立て投資」とも言える。取引先という理由だけで株を買い続ける光景は、持ち合い解消が叫ばれるコーポレートガバナンスの潮流に沿っているとは言いがたい。
取引先持株会を組成する企業は多い。東洋経済が上場企業を調査したところ、少なくとも約500社において取引先持株会とみられる組織が大株主に名を連ねていた。持株会名義の保有割合が少ない企業や、持株会だと判別できない独自の名称を用いる企業もあるため、実際の社数はさらに多いと考えられる。
では、どういった企業が取引先持株会を活用しているのか。次ページからは、有価証券報告書のデータを基に、これまでベールに包まれていた取引先持株会の実態を明らかにする。





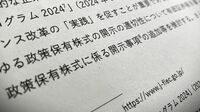





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら