「外部人材の採用」で教育改革を加速、学力調査の結果や生徒指導困難校に表れた変化とは?生駒市と加賀市の事例に見る≪メリットと課題≫
2022年度は国・算・理ともに平均正答率が全国・県を下回っていたが、2023年度に算数で上昇が見られ、ほぼすべての教員が授業改善に取り組むようになった2025年度は3教科とも全国・県を上回った。

「教育大綱で方向性を明確に示したことで、市教委も学校をバックアップしやすくなりました。次はこの学校と同様の成果をほかの学校にも展開することが課題です」と杉山氏は言う。
さらに、杉山氏は義務教育学校の立ち上げに向け、全国の先進事例の視察を企画・実行している。教育長や市長、行政職員、校長、教員などに広く声をかけ、2024年度から2025年度に視察した学校は17校に上る。
視察先の選択や調整は杉山氏が担っており、「従来の行政職員にはない発想やスピード感、人脈を見つける能力がすばらしい」(佐竹氏)と、高く評価されている。

教員経験を持つ「伴走支援」の担当者を採用
第3次教育大綱に掲げる授業改善の実現にあたり、生駒市は現場の教員と直接関わる「伴走者」が必要となった。その役割を担うべく、2025年4月に入庁したのが、元教員の若松俊介氏だ。
若松氏は教職大学院で学校運営や教育行政を学んだ経験も持ち、以前から杉山氏のSNS発信を通じて生駒市の教育改革に関心を持っていた。杉山氏の投稿がきっかけで生駒市の社会人採用を知り、応募したという。
入庁後は市内の学校を訪問する伴走型支援のほか、授業改善に取り組む市内外の教員を対象とした「伴走・越境型研修」を担当。市内の教員約60名、市外の教員約50名を対象にオンライン講座やコミュニティー運営、交流会などを通じた支援を行っている。

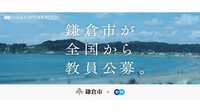





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら