共学化や募集停止続く「女子大」の行方、打つ手はなし?執行部の決断力と資産がカギ 限られる選択肢、大学経営の共通課題でもある
限られる経営の選択肢、求められる決断
これから女子大が取れる施策として、まずは学部学科の構成を今の受験生の志向に合わせることが必須になります。それが大きな投資であることは前述の通りです。
学部学科の再編の先には共学化も視野に入りますし、学部学科の再編と共学化がセットの場合も多く見られます。ただし、共学化も施設設備の改修などハード面での投資も必要になりますので、そのための資産があることが前提になります。
女子大は小規模な大学が多く、十分な資産を持っていない場合もあります。その場合は従来の学部構成のままで存続させるしかありません。実際のところ「人文科学」や「家政」のニーズがまったくないという訳ではありません。今の女子大の入学定員を満たすほどのニーズがないというのが現実ですので、入学定員を現状に合わせて削減する必要があります。
ただし、入学定員の削減は授業料収入の減収になりますので、それに伴いコストカットが必須となります。このコストカットも、誤って授業の質や学生の福利厚生に直結するものを対象としてしまうと、かえって評判を落とし、閉校を早めることになりかねませんので気を付けたいところです。
このほか、従来の学部学科のままでも、カリキュラムを刷新して特色を出し、学科名称を変更する方法もあります。ただ、画期的な教育課程になったとしても、教育内容は最も受験生に伝わりにくい情報の1つですので、評価を得るまでに時間がかかります。それまで大学経営が維持できるかどうか、やはりここでも資産がポイントになってきます。そのため、現有資産の有効活用など授業料以外の収入を増やす施策も考えたいところです。
その観点で、東京科学大学が田町キャンパスの再開発によって、地代収入を得る計画などを見るとうらやましい限りです。余談ですが、以前、都内の大学で留学生から自家用車で通学できるよう、駐車場用に大学の土地の一部を売ってほしいと言われたという話を聞いたことがあります。とあるアジアの国の大富豪のご令嬢だったそうですが、今となってはそれも施策の1つとして考えてもよかったのかもしれません。
ところで、ここでは女子大の話をしていますが、これらは総じて女子大以外の大学にも共通した課題でもあるように思います。いずれにしても、今後の女子大にとって選択肢は限られています。現在の執行部が決断をできるかどうかがカギになります。
(注記のない写真:msv / PIXTA)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

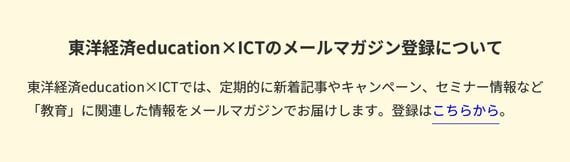































無料会員登録はこちら
ログインはこちら